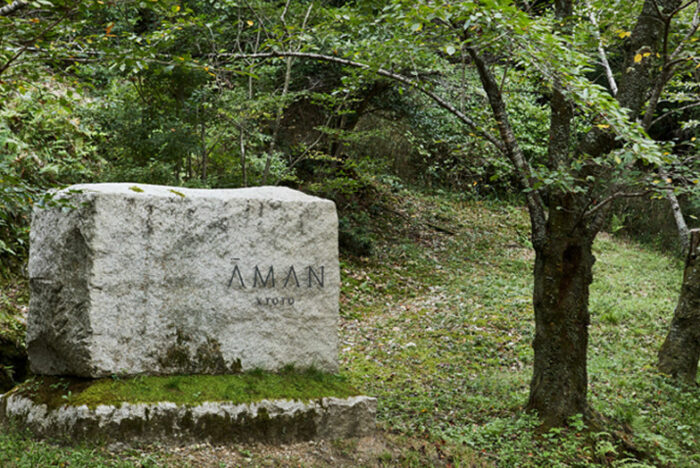アマン京都「鷹庵」で目指す、世界の日本料理への道筋
金沢「銭屋」髙木慎一朗
2025.11.06

京都の奥座敷、鷹峯三山の麓に、かつて西陣織の織屋が約40年もの歳月をかけて育んできた森の庭がある。その庭を、あるがままの自然を生かしたプライベートリゾートで知られるアマンが受け継ぎ、約20年をかけてオープンさせた「アマン京都」、その門前に佇むのが、日本料理レストラン「鷹庵」だ。
金沢の料亭「銭屋」当主・髙木慎一朗さんがプロデュースに立ち、日本料理を世界へ発信する拠点を目指す。髙木さんが見据える「世界の日本料理」への道筋を聞いた。
目次
- ■海外のシェフたちは日本料理のストラクチャーを理解している
- ■今のガストロノミーの潮流にフィットするのは日本料理
- ■外国人がつくる日本料理も認められるタイミングだと思う
- ■日本料理の「なぜ?」に答えられる料理人になる
- ■おいしいだけでなく「すごく楽しかった」という体験をつくる
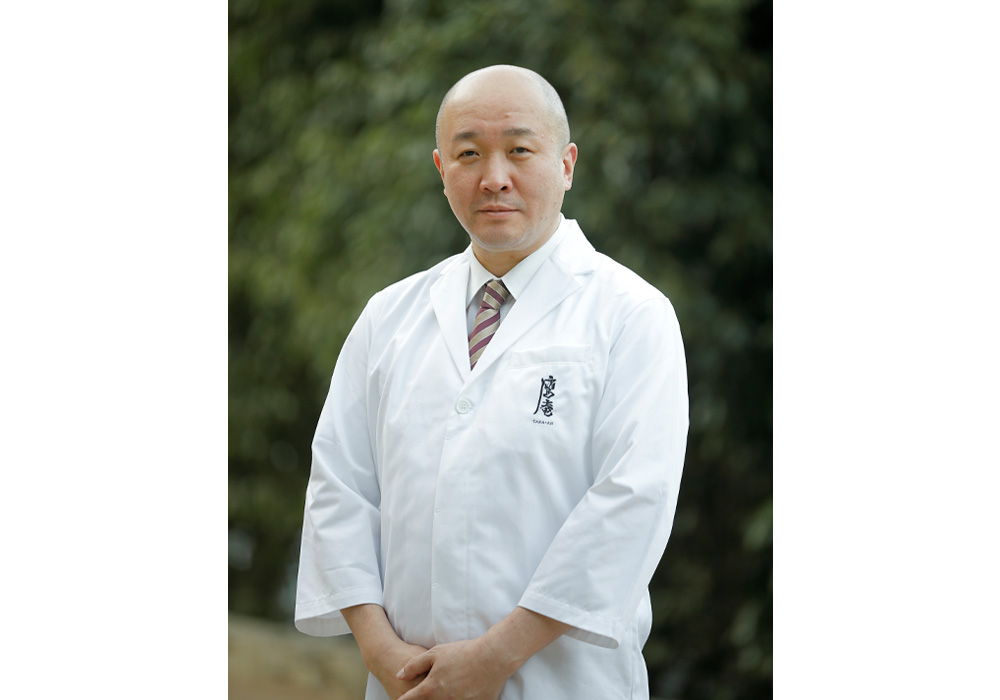
髙木慎一朗(たかぎ・しんいちろう)
1970年、石川県金沢市生まれ。日本料理「銭屋」を営む父のもと生まれ育ち、高校時代に米国へ1年留学。大学卒業後、父の急逝をきっかけに「京都吉兆」に入り、96年に「銭屋」に戻る。2008年、2代目主人に就任。同年、NY日本総領事公邸晩餐会で料理を担当し、以来、世界各地で日本料理の普及・発展に努める。2016年にミシュラン二ツ星を獲得。同年、ルレ・エ・シャトーに加盟。2020年4月、アマン京都の日本料理「鷹庵」総料理長に就任。
海外のシェフたちは日本料理のストラクチャーを理解している
――すしがグローバル化するいっぽうで、日本料理は理解されにくいとよく言われます。髙木さんは20年近く海外で日本料理を作る経験を重ねてこられて、日本料理の現在地をどう捉えていますか?
日本料理というフォーマットはまだまだ定着していませんが、会席料理が海外のシェフ、ガストロノミーに影響を与えているのは事実でしょう。昔に比べ、コースで提供される品数が増え、一皿のポーションが小さくなっているのは、ライフスタイルや嗜好の変化もあるでしょうが、間違いなく会席料理の影響だと思います。
10年くらい前に「UMAMI」という言葉を海外のシェフからよく聞くようになり、そのあたりからだしを使う料理人が増えました。海外のイベントで僕がだしを引いていると、厨房にいる料理人が側に来てずっと見ていますよ。
自分でだしをとるようになったからでしょう、今では植物性の酸(昆布)と動物性の酸(鰹節)を掛け合わせるという日本料理のストラクチャーを理解しているシェフは非常に多いです。その上で、なぜ昆布でなくてはいけないのか、ワカメではだめなのかと聞いてくる。彼らにとって日本料理は、極めてネタの宝庫なんですね。
今のガストロノミーの潮流にフィットするのは日本料理
それと相まって今の料理人は、世界的な健康志向や自然志向、地球環境に配慮するといったテーマを自分に課していますよね。そこに一番フィットするのが日本料理ではないかと思っています。
80年代のフランス料理でご馳走といえばフォワグラとキャビア、鶏はブレス産でなくてはと言われていた。それが今では、地元の鶏を使いたがる。そこに来なくては食べられない料理を出すべきだという発想になったからですが、もともと日本料理では当たり前のことです。
日本料理イコール会席料理といった何か決まった形があるわけではなく、その土地の気候風土を生かして料理にしていくという考え方自体が日本料理。今はそれがライフスタイルとして浸透していますよね?
海外で料理する時は、できる限り現地の食材を使うようにしています。地中海でとれたマグロや何回聞いても覚えられないキノコ、ほうれん草ではなくルーコラを使ってほろ苦い胡麻和えにしたり。今はほうれん草を苦い野菜と思う人はいないでしょうが、自分が駆け出しの頃は苦い野菜で、苦味を抜く仕事がありました。その応用です。
カルガリーで友人シェフらと山へ山菜を採りに行った時は、どれ一つ見たことのない山菜ばかりで彼らは普段ピクルスにして食べるという。僕はそれを、1時間前に採ったばかりで水分をたっぷり含んでいるからと、てんぷらにした。てんぷらは揚げ物ではなく、衣に守られた野菜のもつ水分で加熱する蒸し料理だと話して。
――日本料理の考え方を現地で見せていくということですね。
一口に“日本料理”といっても、フランス料理やイタリア料理もそうであるように、地方料理の集合体で、沖縄も北海道も含めて日本料理。どの地方料理にもポテンシャルはある。会席料理には椀もの、八寸がなくてはというのは形式の問題であって、日本料理が地方料理の総称とするならば、それも一つのスタイルでしかないと思う。
小さな島国でこれほどバリエーションに富んだ食文化がある国は珍しいし、それだけ許容力があるということは、極論ですがNYの日本料理があっても、トリノの日本料理があっても僕はいいと思っています。

外国人がつくる日本料理も認められるタイミングだと思う
――そうした視点に気づいた異ジャンル出身の日本人シェフが、自分の料理を日本料理として発信する動きもあります。
ケープタウンで毎年コラボレーションをしている友人のシェフは、スタイルはフレンチですけど随所に出てくるのはガチな日本料理。金沢にも呼んだことがあるカナダ人シェフも若い頃からフレンチで修業していましたが、日本で居酒屋に感激してカルガリーで居酒屋を開きました。
そういうのを見て本物じゃないという人も多いですけれど、そこは認めるべきタイミングだと僕は思います。それを言うなら1980年代の日本のイタリア料理はどうだったのかと。インチキだったと言われてもおかしくない、でも今の日本のイタリアンは本国より洗練されているくらいレベルが高い。
それに、海外で日本料理店が増えたとしても、日本に行って食べてみたいという思いは絶対にあるはずです。エントランスとなるようなローカル料理になればいいですよね。

日本料理の「なぜ?」に答えられる料理人になる
会席料理はどんなものか説明してくれと言われると、いつも「会席料理はオペラで、すしはソロだ」と喩えます。すしはバイオリンの音、ピアノの音だけに集中すればいい。会席料理はソプラノもアルトもテノールもあって、オーケストラがいて舞台演出、テキスタイル、すべてひっくるめた複合体。理解するにはある程度、勉強や経験が必要です。
ですが、知らない人でも楽しんでもらえるものをプロとして提供しなくてはいけないんじゃないかな。フランス料理を食べるのにフランス革命を知らなきゃ、イタリア料理はルネサンスを知らないと、ではないですよね。
今(取材時は8月半ば)、京都市内の日本料理屋にいくと100発100中鱧が出てきます。そこで、なぜ鱧を出すのかをどう説明するか。
たとえば鱧の骨切り。鱧1匹で背骨腹骨200本以上ありますが、魚の体温は17~18℃。倍の体温の人間が触りながら骨を抜いていったら、いい状態で口に入るわけがない。手を触れるか触れないかで、さっさと骨切りする。普段、包丁は引いて切るけれど、鱧だけ押して切るのは、そのほうがリズムよく均等に切れるから。こうした説明は、オペラや歌舞伎を解説を聞きながら観るのと同じですよね。
――それが日本料理を伝えるということですね。
そもそも日本の文化に興味があって日本に来るわけで、その時点で胸襟をひらいているのだから、我々がどうアプローチするか。オペラとしての会席料理を知りたいという人は間違いなく増えている、そして本質的に理解する人が多いです。すばらしい技術だけでなく、なぜこのスピードでこの角度で包丁を入れるのか。そこに論理的に答えられないとお客さんは納得しない。

おいしいだけでなく「すごく楽しかった」という体験をつくる
2009年にナパ・ヴァレーの三ツ星レストランに呼ばれて、日本料理のディナーをやらせてもらったのですが、サービスチームとのブリーフィングに1時間かかりました。たった5品ですよ。
もちろん、のどぐろは近海にしかいない、水深どれくらいにいる魚で、といった食材の情報はきちんと最初から伝えている、それで十分じゃないかと思う。でも彼らは、自分たちの料理として出すにはもっと情報が必要と、延々と質問してくる。なぜシェフはのどぐろを選んだんだ? 子供の頃から食べているのか?と。
それって説明ではなく、エンターテインしているから必要な情報なんですね。料理がおいしくなるような情報を提供し、会話を楽しむ雰囲気づくりをし、お客さんはたった5品で3時間近くディナーを楽しんでいる。日本料理でもこんな連中と仕事したいなと思いました。
――日本料理を食べて、すごく楽しかったという体験を作っていく場が「鷹庵」ですか?
それが理想です。初めて日本に来た人がまず「ワオ!」となることで、文化に対する興味が開いていく。日本料理が忘れられない思い出になる。技術の意味を知ることで、「学びたい」となる。
これから人口が減る中、日本料理の技術を引き継ぐ人は減っていく。だとしたら、日本でこれほどまでにイタリア料理人、フランス料理人がいる、その逆をやろうよと。NYスタイルでいいんです、カルガリースタイルでいいんです。
日本料理のファンを増やして、日本のイタリアンやフレンチと同じ現象が海外でおこることが夢です。

◎アマン京都「鷹庵」
京都府京都市北区大北山鷹峯町1番
☎075-496-1335
12:00~15:00(最終入店13:00)
18:00~22:00(最終入店20:00)
昼 ¥20,000、夜 ¥40,000(ともにサービス料・税込)
https://www.takaan.jp/