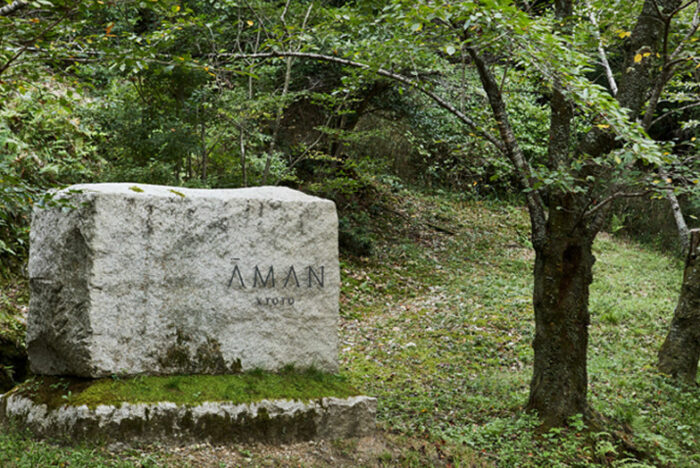パンの原風景を求めて
ブーランジェ 稲垣 信也
2025.02.17

text by Sawako Kimijima / photographs by Masahiro Goda
(写真)「トレジエ」4品種の古代麦が混植された畑から収穫した小麦粉で焼いている。「収穫した麦を翌年蒔くのですが、4品種の間で自然交配していくため、毎年、収穫される麦の性質がどんどん変化していくんです」。それくらい固定させないということだ。ショートミキシング後、台の上で畳んで、バケツに入れて冷蔵庫で14~18時間。復温後、分割して、室温で2時間休ませた後に、窯入れ。
「思い返すと、朝はいつも自分で食パンをトーストして食べていましたね」と笑う。
「パンが持つ雰囲気に憧れがあったのだと思います」
初めてパンを焼いたのは、大学卒業後のアルバイトで。
そこからパン職人の道へ踏み込んだ。
イメージするパン屋が東京にはなくて、山梨のパン屋へ入った。
当時から、稲垣信也がパンに見ているものは、他の職人とは少し違う。

1971年、愛知県生まれ。大学卒業後、「アフタヌーンティールーム」などでのアルバイトを経て、山梨の「プラテーロ」でパン作りを学ぶ。2000年渡仏し、ノルマンディーのエコ・ファーム、バルバリー農園へ。以降、フランス各地の農家を回る中で、農家ならではのパン作りを体験する。2004年からパリの「ル・グルニエ・ア・パン」へ。在籍中に、パティスリーのディプロム、10年ビザなどを取得、責任者の立場も任されるように。2013年、都市再開発プロジェクトのための準備として「レ・メートル・ド・モン・ムーラン」に入る。プロジェクトは中止となり、2016年「ラ・ブーランジュリー・ド・ニル」立ち上げに携わるも退く。現在パリで開店準備中(取材当時)
稲垣の頭の中にはいつも風景がある。
大学時代は経済学部に在籍しながら、絵ばかり描いていた。熱帯魚屋でアルバイトしている時は、水槽の向こうに川の景色を見ていたという。
2000年、パン職人としてフランスへ渡ったのも、パンを取り巻く風景を見るためだった。選んだ修業先がパン屋でなく農家だったのは、パンの原風景を体験したいと望んだからだ。そこにパンの源流があると無意識に思ったからだ。
日本人女性が嫁いでいたノルマンディーのエコ・ファームに知人の伝手で入る。その農場では、風力と太陽光による自家発電によって麦の栽培から薪窯でのパン焼きまでを手掛け、マルシェで販売していた。
「霧雨が降る中、駅まで迎えに来てもらって、農場へ着いてみると、海賊か山賊の家に転がり込んだような心持ちがしました。辺り一面、小麦粉と灰だらけ。そこにゴロッとパンが置かれている。かつて見たことのない景色で、旧石器時代か何かと思うような、狂気すら感じさせる雰囲気だった」 稲垣は即座に「これだ・・・」と思ったという。「ブラン、コンプレ、スペルト」と粉の説明を受けて、心が踊った。
仕事自体は生半可なものではなかった。連日、50㎏の粉袋を担ぎ、生地を捏ねては発酵させ、窯入れと窯出しを繰り返す。薪窯の熱は生き物だ。立ち上がりは噛み付くような熱さ。それが次第に丸くなるのだが、250℃を超える窯から焼き上がったパンを取り出すのに一刻の猶予も許されない。「でないと、窯内の温度が下がってしまって、次のパンが焼けなくなる。彼らは穴が開いた軍手を使い続けていたりするから、とにかく熱くて」。窯入れが数回にわたる日などは24時間以上寝ずにぶっ通しでパンを焼いた。
フランス各地の農家を巡る
なぜ、絵画には背景が必要なのか? 稲垣の話を聞いているとよくわかる。同じパンでも、背景によってパンの意味は違ってくる。都会のパン屋に並んでいるのか、田舎のマルシェなのか、レストランの白い皿の上か、家庭の食卓か。とすれば、パンだけ見ていても、パンを理解したことにならない。稲垣は早い段階でそう感知した。感知した先にフランスの農家パンがあった。
「僕が働いていた時、日本のパン職人のグループが視察に来たんです。その一人が『このパン、どうするんですか?』と聞く」
どうやら売り物に見えなかったらしい。稲垣は胸が痛むと同時に、農家パンを誇らしく思う自分に気付く。ノルマンディーの次の行き先も稲垣は農家に求めた。
「パリで働こうという気はありませんでした。農家の暮らしをもっと見たかった」
次に訪れたのは、南仏モンペリエ近くの田舎町にある羊飼いの家。薪割り、薪運び、羊の世話、ペンキ塗り・・・仕事はいくらでもあった。「パンが焼ける」と言うと、「ぜひ焼いてくれ」と喜ばれた。
「普段の生活の中に入れてもらって、動物の世話をし、畑の手入れをし、パンを焼く。お金を使わない居候です」。そんな生活を3年近く続けた。行き先で知り合った人間が次の行き先を紹介してくれる。数珠つなぎに行き先は向こうからやって来た。「飽きることのない世界が広がっていて、好奇心が刺激され続けました」
結局、3年弱で15軒の農家を回る。南仏を皮切りに、中部フランス、バスク、アルザスと回って、国境を越えてベルギーへ。そこで友人から一報が入る。「信也さん、街に来ないか?」
都市と農家をパンで結ぶ
パリの人気ブーランジュリー「ル・グルニエ・ア・パン」が人を求めているから入らないかという誘いだった。
これまで、バゲットともクロワッサンとも縁のない世界で働いてきた。たぶん、他のブーランジェが体験していないパンの風景を自分は身体の中に持っている。でも、せっかくフランスまで来て、バゲットとクロワッサンを学ばずに帰るのはもったいない。一度は街のパン屋で働いてみよう。そうして、「ル・グルニエ・ア・パン」へ入る。結局、8年半勤め上げ、最終的に店の責任者まで昇格。08年にはパリ右岸のバゲットコンクールで1位も獲得した。
が、稲垣は再び田舎へと戻る。縁あって、南仏ペルピニャン近郊の「レ・メートル・ド・モン・ムーラン」へ。古代麦栽培の先駆者ローラン・フイヤスが営む製粉所兼パン屋で、今度は古代麦に関する知識と経験を積むことになった。稲垣のベクトルは気付くと源流をさかのぼっている。
折りしも、パンの世界は昔へ眼差しを向ける。稲垣が見てきた景色は現代の都市生活者が求める要素を山ほど内包している。「それらをパンに託して都市生活者に手渡すことが自分の役目」と稲垣。パリのパンに、自分が見てきた畑の景色を映し出すのである。今、そのための準備段階に入っている。

◎Shinya pain
41 rue des trois frères 75018 Paris
instagram:@shinyapain_montmartre
木曜〜日曜 16:30〜19:30
※稲垣さんは、2020年6月にパリのモンマルトル地区に「シンヤパン(Shinya Pain)」をオープンしています。(2025年2月編集部追記)
(雑誌『料理通信』2017年6月号掲載)
購入はこちら