地方料理とは何か?
「里山十帖」桑木野恵子×「とおの屋 要」佐々木要太郎
2022.05.16

text by Sawako Kimijima / photographs by Kenji Kudo
料理長就任から4年が経ち、ローカルガストロノミーの担い手としての存在感を高める新潟県南魚沼「里山十帖」の桑木野恵子さん。岩手県遠野市で米の栽培から手掛けてどぶろくを醸し、独創的な料理を供するオーベルジュ「とおの屋 要(よう)」の佐々木要太郎さん。地方を拠点に活躍する2人のコラボイベントが、里山十帖で開かれた。題して、「小さな、小さな、食のシンポジウム 時空を超えた地方料理を目指して」。地方のレストランに熱い視線が注がれる今だからこそ、「地方料理とは何か?」を考えようとの企画である。
ある物がすべて。ないものはどう頑張ってもない。
今、ガストロノミーの潮流は地方から――と言いたくなる空気がある。ジャパンタイムズが2021年、“日本人が選ぶ、世界の人々のための、日本のレストランリスト”と銘打って発表した「Destination Restaurants(デスティネーション・レストラン)」が東京23区と政令指定都市を対象外としたのは象徴的だ。
『自遊人』編集長にして「里山十帖」の創設者、岩佐十良さんはそんな潮流の火付け役と言っていい。2017年、「ローカルガストロノミー」という言葉を世に送り出し、人々の意識を地方へと向けた。
しかし、岩佐さんは最近、心配している。「地方料理が都市料理化しているのではないか。地方料理はなくなっていくのではないか」との危惧である。
確かに地方料理が都市料理化していく要因は十分にある。インターネットやSNSの浸透によって都市と地方の情報格差がなくなった。地方という立地が情報のハンデにならない。むしろ、ガストロノミーの素材主義が強まる中で、産地との距離感や自然環境を優先させて地方で店を開く料理人がいる。海外で修業しても東京ではなく地方で独立する料理人が増えた・・・といった動向が進展するにつれ、地方の料理は都市化していく。
「地方料理とは何か」を考えるにあたって、岩佐さんは、佐々木さんと桑木野さんの2人にキーワードを提示したという。
「全村餓死」。一瞬、ギョッとする言葉だが、春、村民全員が餓死しているのが発見されたということが、江戸時代の天明の大飢饉や天保の大飢饉の際には起きたという。
「地形や気候によっては食材の流通が完全に途絶えたのでしょう。どんなに雪深くても、ウサギやシカ、イノシシなどの動物はいたでしょうから、稲作(米食)比率の高い食生活になっていたことが飢饉に結び付いたのかもしれない」と岩佐さんは推測する。


流通は、地方料理について考える上での大事なポイントだ。流通によって食材も文化も行き来する。地域性は混じり合い、農産物は、流通に耐えるもの、流通先で喜ばれるものへと性質を変えていく。品種改良も流通が促した部分は大きい。
流通の発達が食の変化を推し進めたとするならば、地方料理とは何かを考える時、「流通していない」はひとつのキーワードに違いない。
「その土地にある物がすべてで、その土地にない物はどう頑張ってもない。これが地方食の本質のように思います」
そう語るのは桑木野さんだ。流通していない食材、昔からそこにあった種の動植物を使うことは、土地の厳密な表現法と言えるだろう。
「だからといって、昔からある地方食をそのまま出すのは今の時代に生きる料理人の仕事として違う。もちろん、郷土料理を作れるようになることは大切です。例えば、新潟にはぜんまい煮という料理がありますが、これを一から作ろうと思ったら、知るべきことが山ほどある。ぜんまいはどこに生えているのか、どうやってぜんまいを採るのか、どうやって干すのか、乾燥したぜんまいの戻し方、味の染み込ませ方。郷土料理は土地に蓄積された知恵や文化の結晶であり、土地を理解することです。それらの上に料理を作り上げていくことが、地方で料理を作る意義だと思う」
「限られた食材しかないからこそ、学びと気付きが多い。制約が厳しい環境だからこそ、持てる五感を研ぎ澄まし、第六感までも使い、内に秘める感情や想いを絞り出す。そこからオリジナルが生まれるんだと僕は思う」と語るのは佐々木要太郎さん。「冬、僕の店がある岩手県遠野市は氷点下で雪も降る。使える食材は限られ、乾物、漬物、野生肉、役目を終えた鴨や鳩、家畜たち。そんな中で、先人の知恵から生まれた発酵食・保存食、オリジナルの発酵食材を使って一皿に仕上げていく」
流通網が張り巡らされる以前の土地の様相の上に立って料理を考える時、そこは、食に内在する人知を掘り起こし、未来の食を模索する実験室となる。
人間が不得手とする味も含めてのおいしさ。
桑木野さんは、「暮らしていく中でわかってくることがたくさんある」と語る。
山歩きをしながら職場へ通う。懇意にする農家の畑を訪れてはおじいちゃんと会話する。共同浴場で地域のおばあちゃんたちと語らう。魚沼生まれではない桑木野さんは、暮らしを通して南魚沼に根付く食文化を体得してきた。
「三五八(塩、米麹、米を3:5:8の割合で合わせた漬床)の仕込みには適切な温度や湿度があって、365日OKなわけじゃない。体感的に伝えられてきた地元の当たり前を、お風呂に入りながらおばあちゃんに教えてもらうんです」


暮らした時間が長くなるほどに、より新潟という土地を意識するようになった。
「一皿の完結だけでなくストーリーとしてコース全体を考える大切さや、おいしいとは何かを考える。自分自身は狩猟や採集をしている猟師の感覚で、その時々の旬はもちろん、一つの植物を一年間通して見つめ、追いかけています。数日で終わってしまう新芽や花との真剣勝負もあれば、3年熟成させた青胡桃の新しい側面の発見など、時間の経過が料理の味を作ることにも面白さを感じるようになりました。まぎれもなくこの自然環境のおかげで里山十帖の料理は成り立っている」



イベントが開かれたのは、3月23~25日。「今ここにあるものを使って料理を作る」というテーマのもと、長い冬が終わる時期の食材でコースは組み立てられた。
桑木野さんと要太郎さん、2人が話し合い、練り上げて生み出した料理の数々は、岩佐さんいわく「コース全編通して茶色い(笑)」
確かに禅寺の精進料理のような趣きがある。
口に含むとよくわかる。食材に備わる充実した質感がもたらす歯応えは、口中の滞留時間を長くする。少量でも食べている実感が強い。噛むほどに湧き出る味わいは玉虫色のように複雑だ。“ふわとろ”の対極と言っていい。口の中に長く留まる実在感はまさに命をつなぐ食べ物の様相だ。




「自然な発酵は多味になる」と要太郎さん。最近は発酵がレストランの厨房に入り込み、調理法のひとつとして組み込まれたこともあって、保温器などによる発酵も増えた。そんな機械による発酵からは複雑味が生まれないという。
「発酵には、1.生き抜くための発酵 2.おいしさのための発酵、2つの側面がある」。現代においては圧倒的に後者だが、かつては前者の意味合いが強かった。雪国の発酵は本来、生き抜くための発酵だ。
「そこから生まれるのは、人間が不得手とする味を含めてのおいしさ。土臭さも季節のおいしさの一部。取り除いてしまうのは違う。不得手な味も含めて表現を考える。それが食の喜びの追求なんじゃないか」と要太郎さん。



「地方料理とは何か」をめぐる思考のひとつとして、「都市と地方では料理人が伝えるべきものが違う。都市では旨味という直球を繰り出すけれど、地方でそれをやる必要があるのかなと思う」とは岩佐さんの言葉だ。
土地の味わいを表現する酒造りとは。
要太郎さんは昨夏、米糠を使った酒造りによって新たな米の循環を生み出すプロジェクトを立ち上げた。今回のコラボイベントは、その酒の初披露の場でもあった。
米糠で酒造りと聞いて、食品ロス対策と考えるのは短絡的すぎる。もちろんそういう側面もあるけれど、要太郎さんの構想はもっと大きい。
以前から、要太郎さんは、米を磨く造り方に疑問を抱いていたという。
「土地の味わいを表現するのに米糠が欠かせないと私は考えています。稲は土壌の養分を糧として成長し、米の栄養成分を見ると、米糠は精白米の10~40倍の量を含んでいる。土壌の個性、米の個性の多くが米糠にあるわけです。近年、日本酒業界でも“テロワール”とか“土地の味”といった言葉が語られますが、雑味を取り除くために精米歩合を上げて削ってしまったら、土地の味を表現するのがむずかしい。協会酵母を使用すればなおのこと、土地の味から遠ざかる」
米を削って雑味を減らすのではなく、土を変えて雑味を減らす――要太郎さんはそう考える。すなわち自然栽培による米づくりだ。農薬も肥料も与えない。栄養過多でない健全な土壌で米を育てるのである。フランスのアンリ・ジャイエの哲学に惹かれ、シュタイナーのバイオダイナミック農法を学んでたどり着いた。3年ほど慣行農法と自然農法を並行して実践して比較した結果、無農薬のほうが酵母の力が持続することも発見した。
栽培する米は「遠野一号」。昭和初期に開発されながら普及しなかった地元の品種だ。昨今、次々と誕生している新ブランド米のようにモチ性遺伝子を交配していない、要太郎さんいわく「肥満体質でない米」。なおのこと削る必要がない。要太郎さんが仕込むどぶろくの精米歩合は98%、飯米と同じである。

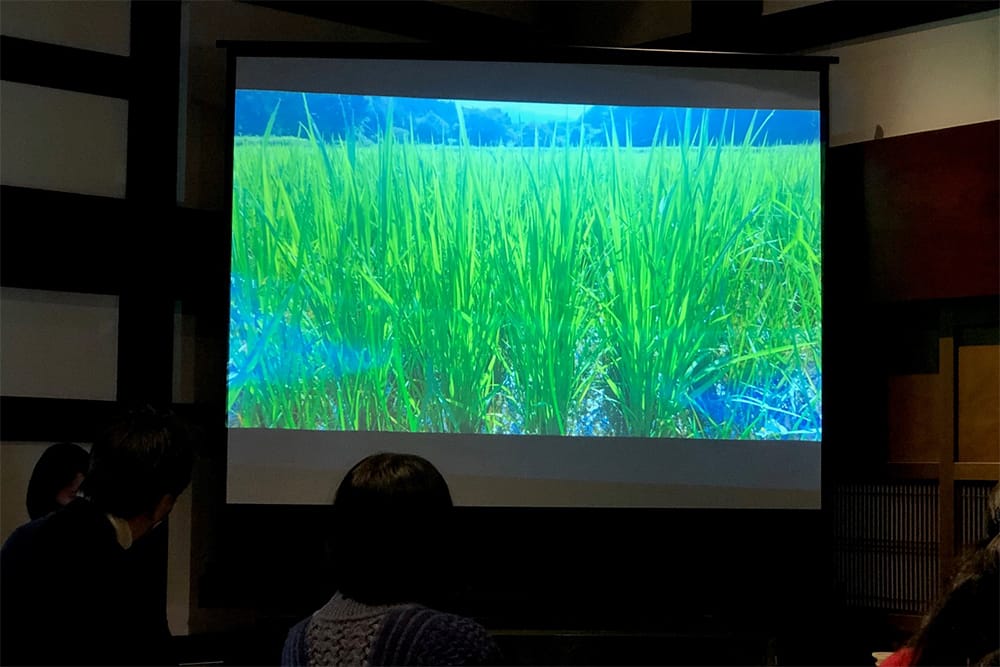
新たに取り組む酒は、米(米糠を含む)と水のみで醸し、袋吊りによる自重で滴る酒だけを集めて、火入れせず瓶に詰める。圧力を掛けないため、手間と時間が掛かり、収量は少なくなる。土壌の個性を存分に映し出した酒に負荷をかけずに提供したいと考えるからだ。

米の消費は減少の一途。要太郎さんは日本の稲作の行方が案じられてならない。農薬や化学肥料といった現代の農法が自然に負荷をかけていることも、後継者不足も懸念される。要太郎流の稲作によって土を健全な状態に戻し、ロスを出すことなく酒や酢を造る。各地でこの取り組みを広めることで稲作文化を守れないか。それがプロジェクトに込めた思いだ。
「食べる」とは、どんなこと?
「食べるということは、昔は命がけだったと思うのです。本来、食べるという行為は、外のものを自分の中に取り入れることであり、それは信頼関係の中で成り立つもの。このイベントでは、対等に食べ物と向き合っていただきたいなと思いました」と桑木野さん。彼女が日々、自然と対峙するからこそ湧いてくる願いなのだろう。


「地方料理とは何か?」というテーマが導いた先は、「食べるとはいかなることか?」であり、現代人が立ち返るべき地点だったように思う。
佐々木要太郎(ささき・ようたろう)
1981年、岩手県生まれ。家業の民宿を継ぎ、2002年、遠野市がどぶろく特区認定地域になったのを機に、独学で無農薬・無肥料の稲作とどぶろく造りに取り組み始める。2011年、オーベルジュ「とおの屋 要」をオープン。2021年、「The World’s 50 Best Discovery」で東北で唯一選出され、また、「The Japan Times Destination Restaurants 2021」で世界の人々のための日本のレストラン10店舗に選ばれる。2019年に農業・醸造部門を法人化して株式会社nondo(農人=農業する人と呑人=お酒を飲む人の両義)を設立し、2021年には「米糠でつくる日本の酒」プロジェクトをクラウトファンディングで立ち上げた。
桑木野恵子(くわきの・けいこ)
1980年、埼玉県生まれ。都内のエステサロン勤務後、海外へ。オーストラリア、ドイツ、インド等を巡り、ヨガと各国のベジタリアン料理を学ぶ。帰国後、都内のヴィーガンレストラン勤務後、自遊人へ入社。温泉(共同浴場)と山歩きを日課に地域のおじいちゃんおばあちゃんと交流し、地に根付く食文化・風土、雪国の暮らしを肌で感じながら、ローカルガストロノミーを料理に表現。2018年、「里山十帖」料理長に就任、2020年「ミシュランガイド新潟2020 特別版」で一ツ星を獲得。2022年には「ゴ・エ・ミヨ2022」で15.5点とテロワール賞を獲得。
◎とおの屋 要(よう)
岩手県遠野市材木町2-17
☎0198-62-7557
昼12:00~13:00、夜18:00~19:00
完全予約制(2日前まで)
http://tonoya-yo.com/
◎里山十帖
新潟県南魚沼市大沢1209−6
☎0570-001-810
予約はこちら
関連リンク









