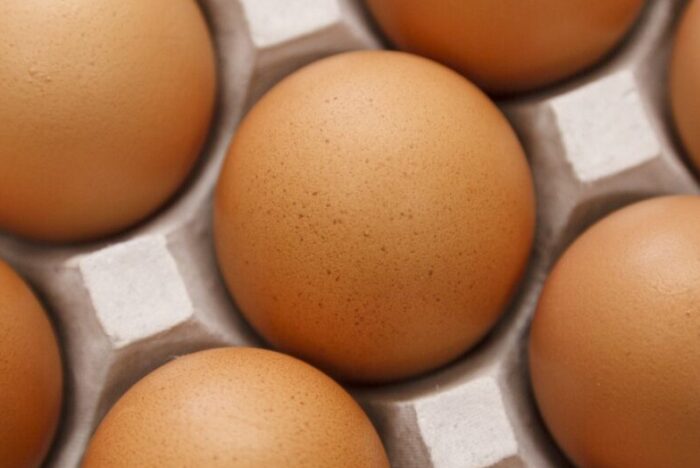味重視の焙煎から生まれた繊細な風味「ゴマ油」
[大阪]未来に届けたい日本の食材 #49
2025.02.06

変わりゆく時代の中で、変わることなく次世代へ伝えたい日本の食材があります。手間を惜しまず、実直に向き合う生産者の手から生まれた個性豊かな食材を、学校法人 服部学園 服部栄養専門学校理事長・校長、服部幸應さんが案内します。
連載:未来に届けたい日本の食材
ゴマには体に必要な栄養素がぎっしり詰まっているのはご存知の通り。中でも最近注目されているのが、強い抗酸化作用を持つゴマリグナンです。セサミンもその一つ。自家焙煎にこだわり、国内栽培にも尽力する老舗メーカー「和田萬」に、社長の和田武大さんを訪ねました。

ゴマの栽培国はコーヒーと似ていて、暑く乾燥したサバンナや赤道付近に多い。うちでは、エチオピアはじめ10カ国から輸入しています。白ゴマのほとんどがアフリカ、中南米、黒は東南アジア、金ゴマはトルコ、エジプトから。有機栽培のものが10%ぐらいです。
ゴマ栽培はほとんどが手作業で、非常に手間がかかる。そのため、日本ではゴマ農家が激減したのですが、2001年から国産ゴマプロジェクトを始め、20以上の府県の契約農家に、無農薬・無化学肥料で栽培してもらっています。それだけでなく、10年から奈良で自家栽培も始めています。5〜6月に種を播き、9月に収穫して干すのですが、ひとつの莢に80粒のゴマが入っています。これが何とも愛おしい。
ゴマ屋はゴミを取り除くのが仕事と言われるほど選別を繰り返します。磁石を使ったり、ふるったり風を当てたり、6種の機械を通し、砂鉄や埃、微細な石を取り除く。さらに焙煎の後にも7回やるので、計13回。肉眼では何もないように見えても、かなりゴミが取れるんです。



ゴマは水洗いし、脱水して焙煎にかかります。煎りゴマ、ゴマ油とも、何より大事にしているのは、この焙煎です。焙煎には熱風式と直火式の2つがあり、煎りゴマは下から熱風を吹き上げて、ゴマ油用のゴマは直火で焙煎します。直火式は筒型のマシンで焙煎しますが、円筒形のフライパンだと思ってください。どちらも、ベテランの職人が張り付いて、その日の温度湿度、その時々のゴマの状態を見極め、風の強さ、庫内の温度を繊細に調整していきます。そう、料理人と同じ発想ですね。
ゴマは生のままだと渋味がある。それが煎ることで香ばしくおいしく変わっていくのですが、煎り具合が弱いと生臭くなりますし、強いと苦く焦げてしまう。見極めは味見です。焙煎の仕上がりを読み、細かい温度調整をしながら、舌で覚えた味に着地させます。熱が芯まで入ると3割ほど粒が膨らむ。これもコーヒーと似ているところですね。
香り高く焙煎したゴマは、圧搾一番搾りという、旨味が一番残る方法で丁寧に搾り、1〜2週間おいて和紙を挟んで濾過します。有機ゴマ油は深煎り、金、黒、白の4種類がありますが、いずれも薄口が特徴。ゴマの香りはしますが、素材の味を邪魔することはありません。オリーブ油のようにバゲットにつけてもおいしいし、サラダやカルパッチョなどにも、旨味とコクを与えてくれます。いろいろな料理に活用なさってみてください。




◎和田萬
大阪府大阪市北区菅原町9-5
☎06-6364-4387
wadaman.com
(雑誌『料理通信』2020年2月号掲載)
購入はこちら
関連リンク