シリーズ「海と魚の今とこれから」キックオフMEETUPレポート
3つの立場から魚の今を語る。
2019.01.10
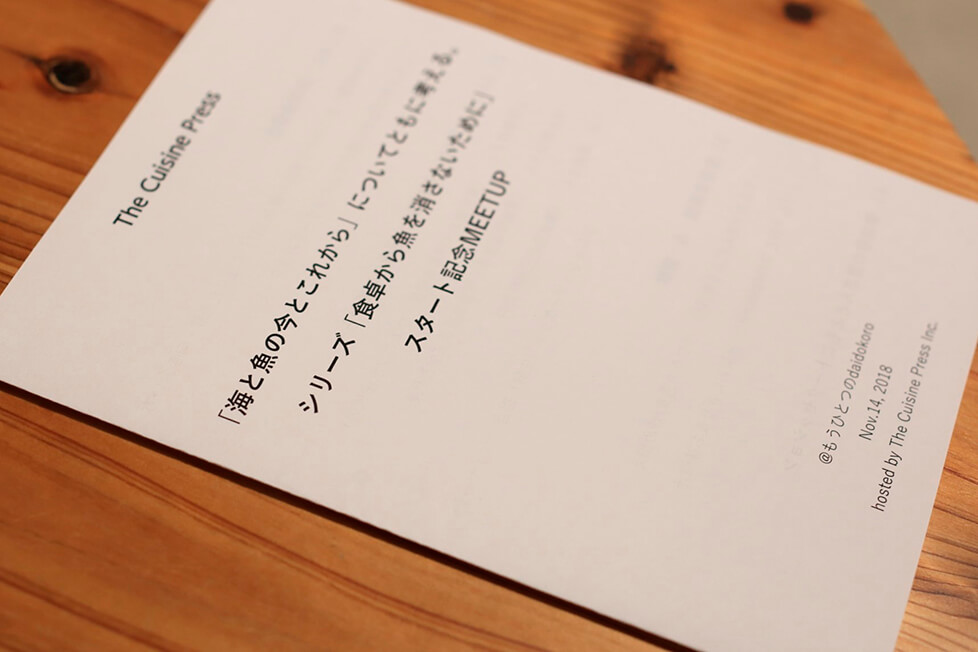
text by Kaori Shibata / photographs by Hide Urabe
魚のニュースが増えています。気候が変わって獲れなくなった、いやいや日本は獲りすぎだ。
世界で魚食の需要が高まる一方、日本人は魚を食べなくなっています。でも聞いてみると、おいしい魚を食べたい日本人は多い。
私たちは、これからもおいしい魚を食べ続けられるのでしょうか?
様々な意見がありますが、共通しているのは、今のままでは食べ続けられない恐れがあるということ。そして、まだやりようはあるということ。料理通信では、見えている現実を積み重ね、できることを考えていきたいと思います。
第一回目は、立場の違う3人の魚の専門家のお話です。元漁師から水産庁職員へ、現在は東京海洋大学客員教授でウエカツ水産代表である上田勝彦さん、宮城県塩釜市で漁業と加工業を営む明豊漁業株式会社代表の松永賢治さん、小売店の立場で魚と向き合う株式会社三越伊勢丹フレッシュマーケットのバイヤー、林真嗣さん。それぞれから見える魚の風景を語っていただきました。

池袋「もうひとつのdaidokoro」を会場にして開催。
「資源管理しやすい魚とそうでない魚」〜全国の海を見てきて〜

全国各地で起きている、でもデータには表れてこない現象をわかりやすく解説するウエカツさん。数字だけ見ていてもダメ、現場の事実の積み上げが大事。
“ウエカツ”の愛称でお馴染みの上田勝彦さんは、「日本の魚食復興」を使命としています。誰に頼まれたわけでもなく芽生えた使命感は、上田さんの特異な職歴によるところが大きいでしょう。長崎県で漁師を経験し、その後は水産庁で25年間、国と漁業の現場を繋ぐ仕事に携わってきました。現在は漁業の現場、流通、小売、飲食店、食卓と魚が関係するすべての場面で、人の育成に携わりそれぞれに適した魚の情報を伝えています。上田さんは、魚を巡る状況を把握するのに「資源データは現実の一側面です。結論を急ぐばかりに問題を単純化すると現実を見誤る」と考えています。
とはいえ、総じて漁獲量が減っているのは紛れもない事実。2014年には太平洋クロマグロ、ニホンウナギが絶滅危惧種に指定されました。この2つほど知られてはいませんが、瀬戸内や東京湾のシャコやアナゴの減少も深刻です。背景には過剰漁獲や気候変化があります。漁業者はもっと資源管理すべきという声が高まる中「東京湾のシャコは資源管理5年目ですが、未だに復活の兆しはありません。一方、日本海側のベニズワイガニのように資源回復してきた魚種もある」と言います。資源管理は、努力しても一概に結果が出るものではない、というのが実感なのです。
また、いつも獲れる場所で獲れなくなることが、必ずしも資源量の減少とは言えないようです。昔から獲れていた富山湾で不漁のブリが、かつては獲れていなかった北海道沖では大漁など、同じ魚種の場所による増減は、各地で起こっています。「そして、根本的なこととして、海域や魚種、漁法の違いで資源管理に向く場合と、そうでない場合があるんです」。

「魚種と漁法が多種多様で複雑な日本の漁業の特性を考慮しなければいけない」とウエカツさん。「海外の資源管理の成功例があてはまるとは限らない」。
現在、世界的に資源管理の手本にすべきとされているのは、ノルウェーやカナダ、アメリカなど日本より北方の海が多いのですが、これについて「北に行くほど魚種が減り、漁の効率が良い」という性質も功を奏していると言います。「北方の鱈や鯖は、一魚種×一漁法で獲れるので資源管理しやすい。しかし、南下するほど魚種は多様になり、一魚種×多漁法や多魚種×一漁法といった漁になります。特定の魚種を管理しようとすると効率は下がる。資源管理は大切ですが、全てに同じルールを押し付けてもうまく行かない。資源管理を続けるには、漁師を支える恒常的な仕組みがないと、彼らにとっては、ただの痩せ我慢になってしまいます」と話します。
漁業の現場だけでなく、小売と食卓の現場も大きく変わりました。「昔は魚屋さんと買う人の間に対話がありました。今、スーパーには切り身魚が置いてあるだけで説明する人はいません。人がいないから数種類のわかりやすい魚種だけに絞って売る。本当は、食べられる魚がまだまだあるのに並ばない」。
上田さんはここ3年間「日本の小売店に、魚を伝えられるスタッフを育てる」ことに力を入れ、食卓に変化を起こそうとしています。
「海や魚のためのルール作りが大事」〜漁と加工の立場から〜

「明豊漁業」の松永賢治さん。漁業と加工、2つの役割を併せ持つ立場からの話には実感がこもります。海と向き合い、消費者とも向き合うジレンマが感じられました。
株式会社明豊は、カツオやビンチョウマグロを主原料にした加工品の製造販売会社です。しかし2011年、東日本大震災が起こると 、原料のカツオが東北の漁業者から入手できなくなりました。そこで、中古の漁船を購入して自ら漁業を始めたのです。松永賢治さんは、漁業部門の子会社、明豊漁業株式会社の社長を務めています。
2016年、東北を拠点とする漁業として初めて、カツオとビンチョウマグロの一本釣りで持続可能な漁業者の認証「海のエコラベル MSC」を取得しました。日本ではまだ3件目という認証を、加工会社が本業の同社がなぜ取得したのでしょうか。
「持続可能な漁業を目指すなんていう志の高いことではなく、営業に行ったスーパーで、認証ラベルをとったら買うって言われたのです。持続可能な漁業が重要だと実感したのは、取得してからです。加工会社がなぜと言われますけれど、加工会社だから取れた。正直、漁業者としてのメリットはないです。認証を取るのにお金がかかりますし、認証マークが付いているからといって、高く売れものでもありません。漁業だけで認証に費用をかけても割に合わない。加工して付加価値を上げられるから費用が賄えるのです。漁業者にも、買う側にも、今の認証制度がベストだとは思っていませんが、海や魚のためにルール作りは大事です。来年は東京オリンピック。持続可能な食料調達基準が、東京でも導入されるかもしれない。オリンピックまでに、持続可能な漁業についての議論が盛り上がるのを期待しています。将来的には、今の認証ルールがさらに良いもの、世間から評価されるものになってほしい」。

「一本釣り」の説明をする松永さん。漁師と魚が1対1で勝負する一本釣りは獲り過ぎない漁法。まさに持続可能な漁の姿です。

松永さんの息子さん達も参加。「今、世界中のみんなで漁業について考えていかなければいけないことを感じてもらえたら」と松永さん。
明豊漁業が取得した持続可能な漁業を認証する制度は、大別すると国際認証と国内認証があり、国際認証として最も知名度が高いのが、MSC(海洋管理協議会)が認証するエコラベルです。同団体は、持続可能な養殖漁業に対してASCのエコラベル認証も行っています。また、国内版認証としては2016年にマリン・エコラベル・ジャパン協議会が、MELの名称で持続可能な漁業者及び流通加工業者を認証する制度が始まりました。東京オリンピックの食料調達基準を満たし、水産物の国内消費の拡大や輸出拡大を目的に、日本の多種多様な水産業事情を汲んだ認証を目指しています。しかしながら、日本での社会的な認知は、どの認証も高いとはいえず、取得した事業者が、市場で優位になる状況ではありません。松永さんが言うように、東京オリンピックの開催で、海外から日本漁業への関心が高まることが、資源管理や認証ルールを活性化する力になるかもしれません。
「魚食拡大に必要なのは話題力」〜小売の視点から〜

株式会社三越伊勢丹フレッシュマーケットのバイヤー、林真嗣さん。「食卓を通して伝えていけることがたくさんある」と考えている。
伊勢丹新宿店の生鮮品を取り扱うバイヤー、林真嗣さんは「お客さまは、魚離れをしたのではなく魚屋離れをしたのだと思う。昔の魚屋さんは、もっと話題を提供できていたはず」と魚売り場の現状を見ています。販売の現場では、食卓で話題にしたいかどうかが購入動機だと言います。
「漁業の現場から伝えられないことを代わって伝える。小売店の役割は、翻訳力と常々思っています。魚に限らないのですが、たくさん並んでいるものの中から選ばれるには、商品にお客様が思い入れを持てるかどうかが大事。それが食卓の話題に繋がります。ファンになれば、長く売れ続ける。それは、野菜、肉も魚も同じです」。

どんな提案をしたら、家庭のテーブルに魚がのるのか、常に考えている。ソーセージや干物など新しい食材の開発も手掛ける。
伊勢丹新宿店の生鮮売り場には、スタイリストと呼ばれる販売員が立ち、知識のあるスタッフがレシピなども伝えています。伝え方に加え、力をいれているのが商品づくりです。水産資源を大切に扱い、魚食のファンを増やせる商品とは何か。これまで、築地では出回らない魚種を地方のお宝魚として販売したり、シェフとコラボレーションして未利用魚をソーセージにしたり、干物を「アタラシイヒモノ」として、洋食メニューに調理できる加工品を作るなどを実施してきました。
「まだまだ結果が出ているとは言えません。でも、難しい話はともかく美味しい魚を食卓に届けたいと思います。肉に比べて、魚は家庭で調理するハードルの高い食材です。だから、なるべくバーを下げることに、これからも挑戦していきたいです」。

玄界灘から届いたばかりのサワラをウエカツさんがその場で捌いてくれた。


サワラを野菜と一緒にフライパンで調理。今、家庭で一番よく使われる調理道具はフライパン。そして、求められているのは野菜料理。魚を時代のニーズにピタリとはめ込む。
「魚をどう食べるか」〜食べ手の立場で〜



参加者のみなさんから、たくさんの質問や意見が。「なんとかしたい」「でも、どうやって」という思いを抱えていることが伝わってきました。


MEETUPに参加してくださった岩手県「ロレオール」伊藤勝康シェフ、Chefs for the Blueメンバーである「salmon & trout」森枝幹シェフからも貴重な意見を寄せていただきました。
現在、日本の魚と米の消費、肉と小麦の消費は連動しています。前者は下降し、後者は上昇しています。魚は家で調理せず、外で食べる食材となりつつあります。
上田さんの話に「魚自体の魅力を語っても魚はそれほど売れない。でも、干物は焼くだけでなく茹でて食べられるというとそれは売れる」というものがありました。これは、今の食べ手と魚の距離を端的に示しているようです。魚を捌いたり、焼いて食べる家庭が、今後急激に増えることは難しい。それでも、出来合いでなく、ワンパターンでもなく、手軽においしく魚を食べたい人々。上田さんは「食べる人は、満遍なくいろいろな魚を食べ、個性を味わい楽しんでほしい」と言います。そのためには、小売の現場も魚種を絞るのでなく広げることが必要です。理想をいえば、需要が特定の魚種に集中しないようにすれば、大きく見て資源的な枯渇を回避する方へ導くことができるかもしれない。そのためには、様々な魚種をおいしく食べる料理や加工の知恵がもっともっと必要です。
たとえば、魚と米の消費、肉と小麦の消費が連動しているのであれば、それを入れ替えられないか、考えてみる。魚と小麦、米と肉という組み合わせで考えてみる。
スーパーに並ぶ魚の切り身に、「魚焼きグリルで焼いて食べることしか想定していない」と感じることがあります。生鮭比率より塩鮭比率が高かったりすると、「ごはんと食べることしか想定していない」と感じます。他にも、目刺し、ちりめんじゃこ、粕漬けなど、ごはん抜きでは登場しにくい食品が並ぶ……日本の魚食文化がいつしか魚の食べ方を制限してしまっているような気もするのです。これだけ食というフィールドに国境がなくなっているのですから、魚をごはんから解放するタイミングでは、とも思います。
目を海外に転じてみれば、知らず知らずのうちに世界に広まった日本の魚食文化が少なからずあります。すしや刺し身は魚を生で食べるおいしさと技を広め、スリミ(カニカマ)はパテ状の魚がパンにも向くことを証明してきました。このサイトでお届けしている「北海シェフからの便り」の主人公、フィリップ・クライスは日本の魚食文化にインスパイアされて「北海シェフ協会」を立ち上げています。
私たちももっと、魚の食べ方、魚との付き合い方を他国からも学び、広い視点で発想していく時期を迎えています。
「この魚はどこから?」、想像を働かせてみましょう。
今回のMEETUPには、魚の加工に携わる人、街の魚屋さんを営む会社の人、漁師の減少を食い止めたいと活動する人、等々、海と食卓の間に立つ人々が多数参加していましたが、抱える危機感は同じでしょう。
獲る人も売る人も食べる人も、立場や見つめるものは違っていても理想とすることは同じはずです。海が健全に保たれること、魚が自然の摂理に従って生息すること、その上に私たち人間の食は成り立っていること。その関係が持続的に営まれていくこと……。
その関係性を傷つけていないか、イメージしてみることは大切です。
そのためには、もっと海や漁の現状を知らなければいけない。漁師さんと食べる人がお互いを知る機会、ファーマーズマーケットの魚版が都市部でできるといいかもしれません。そうしたら、きっと、お互いの事情がわかる近道になるのではないでしょうか。
都市部に住んでいると、正直なところ、海は遠い。まして、漁は海上で行われているため、畑を見に行くようには行けません。だからこそ、知ろうとする気持ちが大切になってくるのだと言えます。
魚を食べる時、この魚はどこから来たのか、どんなふうに獲られたのか、どんなルートで届いてきたのか、ほんの少しのイマジネーションを働かせてみる。それだけで見えてくるものがあるような気がします。
「The Cuisine Press」では、「海と魚の今とこれから」を守るため、そんなイマジネーションの素材をお届けしていきたいと考えています。









