牛肉の新しいスタンダード アイリッシュ グラスフェッドビーフ
2021.06.17

text by Sawako Kimijima / photographs by Masahiro Goda
環境に負荷をかけない、地域資源を生かした循環型の食料生産システムが求められる中で、アイリッシュ グラスフェッドビーフが注目を集めています。
牛肉の目利きとして知られる「ヴァッカロッサ」渡邊雅之シェフとアイルランド政府食糧庁「Bord Bia(ボード・ビア)」のジャパン マネージャーであるジョー・ムーアさんに、これからの畜産のあり方を見据えながら、アイリッシュ グラスフェッドビーフの優位性を語り合っていただきました。
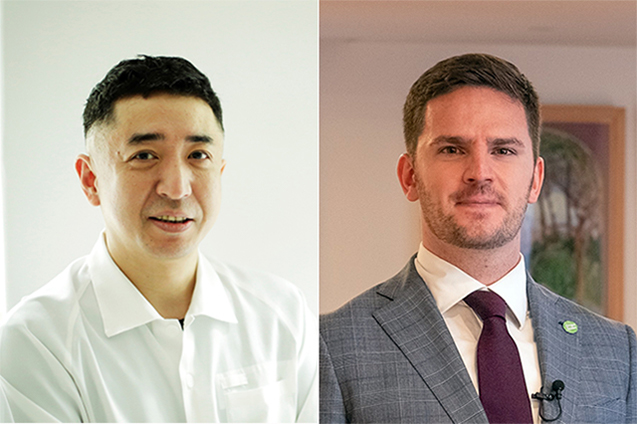
(写真左)「ヴァッカロッサ」渡邊雅之シェフ (写真右)Joe Moore ジョー・ムーア氏 アイルランド政府食糧庁「Bord Bia」ジャパン マネジャー
恵まれた環境を活かす牧草飼育。
渡邊:アイリッシュ グラスフェッドビーフに初めて接したのが2年前。その時、現地の生産体制などをしつこくお聞きしたんですよね。今日はいろいろとお話を伺えることをとても楽しみにしています。
ジョー:覚えています(笑)。
渡邊:僕は20代の頃に牛肉に興味を持ち、以来、牛肉を探求し続けてきました。料理修業の傍ら、芝浦の食肉市場で働いたり、2年間のイタリア修業中には欧州の肉食文化も体験して、「赤身肉をどうおいしく食べさせるか」を自分の仕事の真ん中に置こうと決めた。店名の「VACCA ROSSA」とはイタリア語で「赤身の牛肉」という意味です。そんな中でたどり着いた答えが薪火で塊肉を焼くという調理法。この調理法は、調理の幅が狭く、味付けは塩のみで、ただ焼くだけ。但し、いかに焼き上げるかで味が決まる。その分、肉質の把握が重要になります。だから、扱う肉については、生育段階から知りたいんですね。
食材のバックグラウンドを知ろうと努めるのには、もうひとつ理由があります。1990年代後半、世界的にBSEが問題になった時、僕は料理人としてまさに渦中にいた。当時の体験を通して、食材の健全さが何より大事と痛感した。健康で安全に育てられたものでなければ提供しないと決めたんです。
ジョー:今日はちょうど良い機会ですので、詳しくご説明しましょう。アイルランドの国土は北海道とほぼ同じサイズで、人口は約500万人。でありながら、2500万人分の食料を生産し、その90%を輸出しています。農業で経済が成り立っている国なんですね。背景にあるのが国土の約8割を占める草地と年間を通して安定した気候です。平均最高気温約13.3℃、平均最低気温約6.4℃、1年中降雨が多くて、草の成長を促します。1年のうち10カ月は草が育つので、動物の飼育に適しています。
渡邊:すばらしい環境ですね。“穀物は人間に、動物には草を”が僕の考え(笑)。牛本来の食事は草で、それも乾いた草ではなく、生の草を食べたいんだと思うんですよ。
ジョー:アイルランドでは年間9~10カ月を放牧で育てます。
渡邊:それ以外は牛舎ですか?
ジョー:はい。日本ほどではないけれど、冬はそこそこ寒く、草の成長も止まるので、広い牛舎に入れて、夏の間に仕込んでおいたサイレージ(発酵させた飼料)と少しばかりの穀物を与えます。
渡邊:農家は牛の飼育と草の管理を並行して行なうわけですね。
ジョー:ええ、草の管理ができなければ牛の管理もできません。アイルランドでは「パドックシステム」によって放牧を行ないます。パドックシステムというのは、草地を区画に分けて、区画ごとに牛を移動させていく放牧法です。A区画の草を牛が食べ尽くしたら、B区画へ移動。B区画を食べ尽くしたら、C区画へ移動。そうやって草の生育と放牧を並行して行なう。農場の規模にもよりますが、3日間ごとに場所を移動させ、計30日間各区画に牛が立ち入らず牧草が成長できる期間を確保しています。最近ではアプリも開発されて、生産者はアプリで草地の管理をしています。
渡邊:アイリッシュ グラスフェッドビーフは、年間通して使うと、季節によって味が変わるのを感じます。草の質が季節で変わるから、それを食べている牛の肉質も変わるんだなって。牛とは環境動物であると実感しますね。

パドックシステムのフィールド。約3日ごとに牛を区画移動させる。牧草を育てつつ放牧を続ける方法だ。
国と農家が一丸となって進めるサステナブル・プログラム。
ジョー:アイルランドでは牛を育てている畜産農家が約5万1500軒あります。その99%が家族経営で、1農場あたりの飼育頭数が平均17頭。76%の農場は1haあたり2頭未満という飼育密度の低さも自慢です。
渡邊:おいしい肉の生産者を辿っていくと、小さい農場が家族で育てているケースが多い。愛情のかけ方が手厚く、毎日同じ人と顔を合わせている安心感があるのでしょう、牛もストレスがなくてリラックスしている。アイリッシュ グラスフェッドビーフを初めて食べた時、良い肉だなぁと思ったのですが、理由が理解できました。それで経営は成り立つんですか?
ジョー:ほとんどの農家が畜産と野菜などの栽培を兼業しています。
渡邊:なるほど。僕は土佐あかうしの生産者さんとお付き合いがあって、野菜や米の栽培の傍らで牛を育てる試みに関わっています。畜産に専念するとどうしても集約的な飼育形態で濃厚飼料を与えて肥育することになる。それよりも、野菜栽培や稲作と並行して数頭を飼い、草や稲藁を食べさせ、あまり手をかけずに育てたほうが、牛本来の生態に適っているし、農家さんも取り組みやすいんじゃないかって。小さな試みですが、次の世代が少しでも畜産に親しみを持ってほしくて。
ジョー:いいですね。アイルランドでは10年ほど前に、国家的食品サステナビリティプログラム「オリジングリーン」を政府主導で立ち上げて、私たちボード・ビアが監督しています。畜産農家から小売業者まで、生産と供給の全体に関わるプログラムで、環境の保護、エネルギーの使用と排出、廃棄物、生物多様性、地域社会への取り組みなど多岐にわたって持続可能性を実現しようとするプログラムです。たとえば、牛肉のトレーサビリティを徹底するため、個体識別情報、出生からと畜場に至るまでの移動に関する全データなど、政府による全国的な一元管理がされています。人間より牛のほうがよほど厳密なパスポートを持っているほど(笑)。
「アイリッシュ グラスフェッドビーフ」を名乗るには、個々の牛が一生で摂取する飼料の少なくとも90%は牧草でなければならない、一生の大部分(年平均220日)を放牧で過ごす、牧草以外の飼料や濃厚飼料は全摂取量の最大10%まで、という基準も設けられています。「オリジングリーン」のメンバーになると、ボード・ビアから資金援助が受けられます。プログラムへの参加は自由意志ですが、第三者が監査に入って実施状況の評価をしますので、実効性は高いですね。
渡邊:どのくらいの農家が参加しているんですか?
ジョー:牛の飼育農家は90%、酪農家は95%が加盟しています。

アイルランドを特徴づけるなだらかな丘陵と緑豊かな草地が舞台。牛たちはのびのびと育つ。

背後に見えるのは風力発電の風車。再生可能エネルギーへの取り組みなど、アイルランドの環境意識は高い。
ジョー:温暖化による気候変動が世界的な社会課題である今、CO2排出の点で牛の飼育は問題視されています。畜産は地球環境的にサステナブルではないといった見方もあるだけに、持続可能性への取り組みは真剣です。現在発表されているデータで言えば、2013年と比べて2014年の牛肉生産に関わるCO2排出量は5%削減、2012年から2017年までの5年間で単位生産量あたりのエネルギー消費が11%、水の使用量は17%削減できています。
渡邊:国と農家が一丸となって取り組んでいるところがうらやましい限りです。
自然の中で育った牛の個性を生かす焼き方を。
渡邊:僕が肉を調理する上で大切にしているのは「噛み心地」です。噛む度に旨味が広がって、いつまでも噛み続けていたくなる味わいを提供したい。そのポテンシャルがある肉を選び、噛み心地を実現するように焼き上げます。アイリッシュ グラスフェッドビーフには食べ続けたくなる噛み心地がありますね。

「ヴァッカロッサ」では、肉が店に届くと状態を見ながら専用の冷蔵庫で1週間から10日ほど寝かせて使う。
渡邊:日本は箸で食べる文化なので、やわらかくて口の中で溶けるような肉質に人気が集まります。加えて、霜降りの入り具合でA5、A4といったランク付けをするため、赤身肉は下に見られがち。肉食の歴史が浅いせいもあって、肉の良し悪しを計る「ものさし」がひとつしかないんですね。僕はそれがもどかしい。良い肉とは何か? サシが多いほうが良いのか、赤身が良いのか、グレインフェッドが良いのか、グラスフェッドが良いのか、品種、月齢、雄雌、経産、非経産、等々、良い肉の要件は様々です。僕たちの世代で肉のものさしを増やして、多様な価値観を提示できたらいいなと思います。何より、健康な牛を育てることが経済価値を上げるんだという考え方を広めたい。その点、アイルランドはお手本です。
ところで、アイルランドのみなさんは普段どのように牛肉を食べているのですか?
ジョー:ステーキですね。サーロインをフライパンで、リブロ―スをオーブンでローストにする。あとはバーガーでしょうか。
渡邊:アイリッシュ グラスフェッドビーフは塊か厚切りで焼くほうがおいしいですね。牧草肉は鉄分が多く、焼き色が付きやすいので、焦がさないように、こまめにひっくり返して、薄い焼き色を重ねながら火を入れていきます。よく最初に表面を焼き固めると言われますが、それでは筋繊維が硬直してしまい、ナイフを入れた時に肉汁が出てしまう。肉汁を細胞内に抱え込ませたまま焼き上げるのが僕の目指す焼き方で、すると噛んだ時に口中で肉汁があふれ出す。そのためには、筋繊維が硬直しないように、こまめに返しながら火を入れることが大切です。

アイリッシュ グラスフェッドビーフのTボーン約800gを薪火で焼く。表面にオリーブ油を塗って炉の上へ。

こまめに返して、薄い焼き色を重ねる感覚で火を入れていく。筋繊維を硬直させない、つまり焼き縮みさせず、やわらかい状態を保ったまま焼き上げるのがポイント。

焼き縮みさせない意味でも、骨付きで焼くのは理に適っている。
渡邊:何人も生産者に会って気付いたのですが、おいしい肉は愛情深い生産者に育てられているし、そういう生産者は環境を大事にしています。その様子を見ているうちに、僕たち料理人は、ミディアムとかレアとか焼き加減ありきではなく、個々の肉質に合わせて焼き加減を決めるべきだと思うようになりました。肉の個性を生かす、個々の牛の違いを楽しむ焼き方です。調理って、そういうことなんじゃないかって。
ジョー:素材を生かす、素材に合わせて技術を変える。日本人らしい考え方ですね。
渡邊:僕たちは、牛の一生の最後を担っているのだと思います。だから、彼らを取り巻く環境を知り、彼らが生まれたところから知って扱わなければ。僕が骨付きで調理するのは、そのほうがおいしいからということもありますが、生き物なんだよってことを皿の上まで届けたいとの思いもあるんです。
ジョー:今日は良い話を聞くことができました。

アイリッシュ グラスフェッドビーフのTボーンステーキ。健康に育ったことがひと目でわかる艶やかな赤身肉。「緻密で凝縮した味わい、食べ心地の良い肉質」と渡邊シェフは太鼓判を押す。
渡邊雅之
1969年生まれ。渋谷「トゥリオ」で7年間修業。その間、イタリア旅行中に出会ったビステッカに魅了され、レストラン勤めの傍ら、芝浦の食肉市場で2カ月間、無給で働く。イタリアへ渡り、トスカーナ州「ラ・キウーザ」で2年間働いて帰国。2002年青山一丁目に「ベッカッチャ」をオープン。2010年12月六本木に移転、2013年から現店。牛肉の探求を続け、品種、飼育法、解体、熟成、火入れと多面的な観点から知見を深めている。根底にある考え方は“サステナブルな畜産が牛肉本来の味わいをつくる”。
◎ヴァッカロッサ
東京都港区赤坂6-4-11 ドミエメロード 1F
☎:03-6435-5670
http://vaccarossa.com/
*アイリッシュ グラスフェッドビーフの提供は不定期です。ご希望の場合はお店に直接お問い合わせください。
Joe Moore(ジョー・ムーア)
アイルランド政府食糧庁「Bord Bia(ボード・ビア)」ジャパン マネージャー
1988年生まれ。アイルランド中央部キャバン州出身。JETプログラムで来日し、新潟県柏崎市で英語教師として勤務。アイルランド帰国後、日本大使館に1年間勤務、さらに日本とアイルランドの科学研究交流プログラムのコーディネーターを務めるなど、日本とアイルランドの関係を深める事業を数多く手掛ける。U19日本代表ラグビーチームのアイルランド訪問時に通訳兼アシスタント・マネジャー、2018年のU20ラグビーワールドカップでは日本代表チームの通訳を務める。2019年から現職。
◎「アイリッシュ グラスフェッドビーフ」に関するお問い合わせ
アイルランド政府食糧庁 Bord Bia(ボード・ビア)
☎:03-3263-0611
Email:tokyo@bordbia.ie
https://irishbeef.jp/









