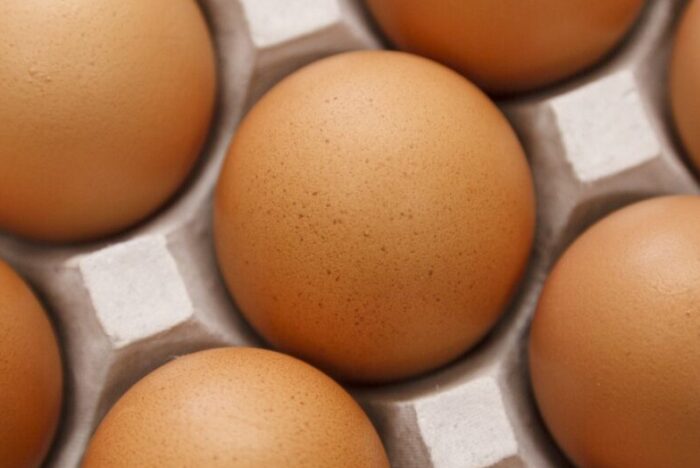日本 [群馬]
食の根幹を手放さない農業を若手につなぐ 古代米
未来に届けたい日本の食材 #16 古代米
2022.05.06
![日本 [群馬] 食の根幹を手放さない農業を若手につなぐ 未来に届けたい日本の食材 #16 古代米](https://r-tsushin.com/wp-content/uploads/2022/05/hattori_yukio16_01.jpg)
変わりゆく時代の中で、変わることなく次世代へ伝えたい日本の食材があります。手間を惜しまず、実直に向き合う生産者の手から生まれた個性豊かな食材を、学校法人 服部学園 服部栄養専門学校理事長・校長、服部幸應さんが案内します。
連載:未来に届けたい日本の食材
1990年、奥さんの病気をきっかけに、有機農業に乗り出した浦部修・真弓夫妻。日本の食文化を培ってきた稲作こそ大事と、環境保全型の農業に取り組んでいます。数々の困難を乗り越えながら、確固たる信念を貫く「古代米浦部農園」に、代表の真弓さんを訪ねます。

黒米の稲は浦部さんの肩よりも高い。栽培の苦労がしのばれる。
難病を抱えていた私は、安全な米と味噌が欲しかった。でも、なかなか見つからない。ならば、自分たちで作ろう。それが私たちの農業の始まりでした。夫は東京まで片道2時間半をかけて通勤しながら、深夜まで農作業という過酷な日々を長く続けてくれました。そんな夫を少しでも手伝いたいと田んぼに出るうち、気付けば元気を取り戻していました。
私たちが目指したのは、米、麦、大豆で成り立つ農家です。野菜や果物は長期備蓄が難しい作物。米、麦、大豆こそ食の根幹、ことに米は日本人の命の根っこを支えるものです。そして、1年でも2年でも保管できるから、外国に頼らずとも食糧を蓄えることができる。まさに、日本の農の屋台骨になるべきもの。しかし、米農家の多くは70代。収益が低いため後継者がなく、耕作放棄する田んぼも多かった。夫が兼業から専業になった時、世襲による後継ではなく、技術を、また考え方を受け継ぐ事業継承をと、法人化を図りました。血縁に頼らず、また、後進を育成しながら、健全な有機農業をさらに推し進めていくことになったのです。
私の体が少しよくなった頃、古代米との出合いがありました。作り手がいなくて、もうこれしかないという種籾を譲り受け、栽培を始めたのです。圃場を見ていただいておわかりのように、古代米、特に黒米は肩を超えるほど背が高い。穂が出る時期がバラバラならば、熟す時期もバラバラ。倒れやすいし、収量も少ない。非常に育てにくいのですが、原種ゆえの力強さ、生命力に溢れ、滋味深く、機能性も高い。まさに命の源です。

多品種で早生から晩生まで栽培。古代米は5月が田植え、11月が収穫、その他の米は6月に田植え、10月に収穫と1カ月の開きがある。作業時期が分散されるので、20ヘクタールの圃場を4人で経営していくことができる。写真は緑米の稲穂。

コンバインを操って稲刈りをするのは28歳の女子。浦部農園では、初めて農業に携わる若い世代を積極的に受け入れている。

(写真左)古代米は稲穂が黒い。ここ数年で全国に広がっている田んぼアートで使用されているのも古代米の稲だ。
(写真右)稲の内側はミルクのような液体から徐々に固形にかたまっていく。収穫を2週間後に控えた稲は、指先で簡単に潰れるほどまだ柔らかい。
現在、圃場は20ヘクタール。スタッフ4人なので、担当は1人5ヘクタール。それぞれがきちんと管理できないとペイしない。助成金に頼らず、売り上げでもって経営するにはどうするか。多品種で早生から晩生までしっかりと栽培する。販売も小袋化して、消費者に入り口を作る。また、米ヌカを堆肥や化粧品メーカーに卸す、さらに自社だけで流通にのせるには量が足りない余剰米は、関東一円の有機米栽培者へ集荷をかけ、まとめてから大手流通にのせるなど、能動的に物流にも関わり、収益を生み出しています。
これからの農業は、社会情勢と同様、発展するのではなく、いかに持続していくかだと思います。1950年に20億だった人口が現在は77億。豊かになってきたことによる食糧危機が起こっています。今こそ、日本人の命を養う米食に立ち戻る時ではないでしょうか。

稲作だけで経営をしていくため、浦部さんは関東の有機農業者の余剰米を束ねて、大手の需要に応えるための拠点を自社で作り、日本政策金融公庫の「輝く経営大賞」に選ばれた。

古代米、大豆、麦など使いやすい小袋も充実。県内の道の駅などでも購入できる
◎古代米浦部農園
群馬県藤岡市鮎川337
☎0274-23-8770
Facebook:有限会社古代米浦部農園
(雑誌『料理通信』2019年1月号掲載)
◎購入サイト