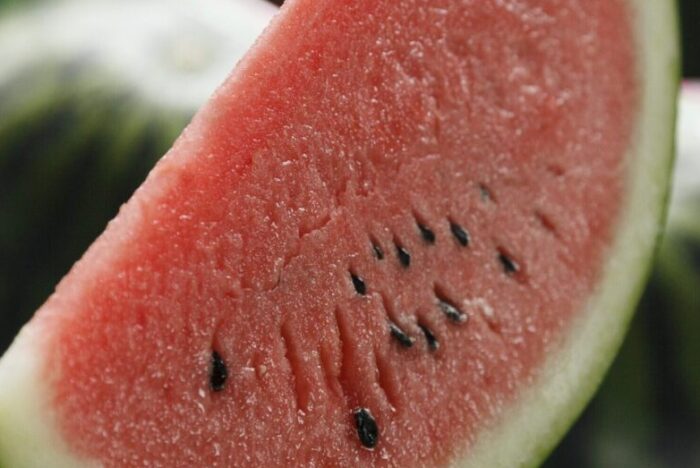日本 [茨城]
東京から1時間圏の産地の魅力
シェフたちの茨城生産者ツアー
2019.10.21

全国から食材が集まる日本の食の要所・東京都中央卸売市場の青果部門で、取扱高日本一を誇るのが茨城県。
9月中旬の早朝。まだ残暑が尾を引く東京からバスに乗って1時間ほど進むと、窓の向こうには色付いた稲穂の黄色いグラデーションが広がっていた。東京では曖昧だった季節の移り変わりが、茨城県ではこんなにも明確だ。色鮮やかな田畑の景色が、実りの秋の訪れを教えてくれた。

全国から食材が集まる日本の食の要所・東京都中央卸売市場の青果部門で、取扱高日本一を誇るのが茨城県。
茨城県のレンコン、メロンなどは、10年以上全国一位の産出額だ。そんな農業大県である茨城の豊かな産地を、東京の食のプロたちと訪ねた。
豊富な水と丹念な土壌づくりで生まれる浮島れんこん。
茨城県の南部にある霞ヶ浦は、琵琶湖に次ぐ日本第二の大きさを誇り、水量も豊か。もともと粒子の細かな土壌を生かし、サトウキビの搾りかすや堆肥などを加えることでさらにミネラル豊富な泥を作っている。だからここでは、味ののった、まるっと太ったレンコンが育つ。
JA稲敷の蓮根部 浮島支部、高須仁さんが出荷までの様子を詳しく教えてくれた。「レンコンは9月の下旬頃までにほぼ成長を終え、その後は田んぼの中で寝かせます。レンコンのデンプン質を糖に変化させて出荷するのです。晩夏や初秋のものは比較的さっぱりした味わいですが、11月頃から糖度がぐっと上がり、甘味も増していきます」

JA稲敷では、部員全員が環境にやさしい生産に取り組むエコファーマーを取得。一部の生産者は農薬や化学肥料を50%以下に抑え「茨城県特別栽培農産物」の認証を受けている。

浮島れんこんは美しい乳白色で瑞々しく、ほのかな甘味があるのが特徴。
地元では、節によって調理法を変えて食べているそうだ。「一番端の小ぶりな節は、あっさりでしゃきしゃき。軽い歯触りを生かして丸ごと甘辛く煮たり、薄切りにして甘酢で仕上げたりします。2、3節目は加熱することでむっちりした柔らかさが楽しめるので、煮物や揚げ物向き。甘味や粘りを生かして、味噌仕立ての汁にダイレクトにすりおろす、こんこん汁という地元料理もあります」。茨城からすぐの東京なら、掘り立ての瑞々しい状態でその日のうちに届けられる。「清澄白河フジマル醸造所」オーナーの藤丸智史さんは「朝の新鮮な掘り立てを使えるのは嬉しい。節ごとの違いはもちろん、縦横の切り方の違いでも食感がまったく違ってくるのがレンコンの面白さ。その違いを楽しむ料理を考えたい」とさっそく料理のイメージを膨らませていた。

朝掘りのれんこんを手に説明してくれたJA稲敷の蓮根部 浮島支部、高須仁さん(右)。

丸ごと使った煮物は、ほくっとした食感と特有の粘りが糸を引く。
無肥料無農薬で30年以上。作物の生育に人間が合わせる農業。
農業の盛んな土地だからこそ、農家の考え方も様々。県内には、日曜ごとにオーガニック・ファーマーズ・マーケットが開かれていて、生産者・生活者ともにオーガニック意識が高いつくばエリアもある。行方市で30年以上農業を営む仲居農園の社長、仲居主一さんは、農薬はもちろん肥料も加えないという型破りな方法で、カブや小松菜、ナシウリ、里芋、サツマイモなどを育てている。

訪れた9月下旬は、小振りのサツマイモが実っていた。これから丹念に成長を見守る。

仲居農園の仲居主一さん(右)と息子の久さん(左)。野菜を子供のように語る主一さんの話には熱がこもる。
「人間が土壌に手を加えて作物を育てるのでなく、作物が自分の力で育っていくのを見守るのが本来の野菜作り。肥料を加えて生育を急がせても、決して味わいのある野菜はできない」というのが、仲居さんの考え。だから、無肥料無農薬を実践する。
農園の二代目・仲居久さんは、「うちの土壌に合う野菜の一つがナシウリ。ナシのようなシャキッとした歯応えと瑞々しさ、ウリやキュウリのような爽やかな香りがあって、個性的です」と、切りたてを食べさせてくれた。

無農薬無肥料での栽培は、年によって出来不出来があるが、想像を超える未知の味わいに出会う可能性も秘める。

「ジューシーなナシウリは、ピクルスにするときっと面白い。冬のカブなど、他の無肥料無農薬野菜もぜひ味わってみたい」とザ・ペニンシュラ東京「ピーター」シェフの桐山正輝さん
光センサーでメロンの糖度を管理。若手農家の多さも特徴。
農業に限らず、今の日本が抱えている問題のひとつが人材不足。高齢化による後継ぎ不足も多い。ところが、茨城県鉾田市旭地区の農業就労者の平均年齢は他よりもぐっと若く、平均で50歳台だ。メロン生産量日本一の茨城県の中でも中心的な産地である旭地区では、その理由の一端が垣間見えた。

父から畑を受け継いだ、アールスメロン部会 生産者、佐伯賢一さん。
旭地区は、昼夜の寒暖差が大きく、土壌は水はけや通気性が良いため、乾くのも速い。メロンは熟す期間、水分が少ないほうが甘くなる性質を持っていて、この土壌はまさに糖度の高いメロン栽培に向いている。恵まれた環境のもと、50年以上に渡りメロン栽培がなされてきた。
訪れたメロン畑で、JA茨城旭村営農販売課長の須加野弘さんは、「アールスメロンは一日で表面の網目模様が変わるほど繊細。収穫前は一つずつ新聞紙で覆い、紫外線で果皮の色が焼けないようにするなど手がかかります。さらに、見た目では糖度や熟度がわかりにくいのも出荷の際の悩み。そこで、JA茨城旭村では光センサーを導入し、出荷前のメロンの糖度や熟度を一斉にチェックして、基準値をクリアしたものだけを出荷するようにしたのです」。

1本の木に数個成るアールスメロンだが、旭地区では一番良い実1つだけを残し、他を摘み取って栽培する。

「旭地区のメロン栽培には若手農家が増えており、活気がある」と須加野弘さん(左)

大規模な光センサーの検品場。地元の小学校などが社会見学によく訪れる。通路には見学した小学生からのお礼の手紙が壁いっぱいに貼ってあり、地元の誇りを感じる。
JA茨城旭村では、このメロンの分業体制のおかげで農家はメロンの育成から出荷までに集中すればよく、仕事の負担が減った。結果、旭地区全体の収穫や品質が安定し、収入も一定額以上を保てるようになった。若手農家の悩みのタネである収入面の不安も、組織全体で分業化することで解消し、旭地区全体に活気も生まれている。

切り立てのメロンは果肉がしっかり、香り豊かでさっぱりと上品な甘さが印象的。

JA茨城旭村の営農販売課長須加野弘さん(中央・左)、アールスメロン部会長佐伯幸一さん(中央・右)。「オトメ、アンデス、クインシー、アールスなど、様々な種類のメロンを手掛け、高い品質のものだけを出荷できる。JAのチームワークが、私たちの強みです」

「イル テアトリーノ ダ サローネ」シェフの北野敏庸さんは「甘味もありつつ、ウリの爽やかさもある。キュウリとタコとメロンのサラダなど、料理にもぜひ使ってみたい」と、イタリア料理の素材としての魅力を感じていた。
栗の名産地・笠間が仕掛ける0℃貯蔵。
茨城県は栽培面積・収穫量ともに全国一位の栗の産地だが、その代表が笠間市だ。盆地特有の寒暖差のある気候に加え、花崗岩質の土壌や黒土が栗栽培に適している。収穫が始まったばかりのJA常陸を訪ねると、まさに早生種の丹沢が箱詰めされていた。
ここで驚きなのが、日本で唯一、栗の大きさや重さを判別する機械が導入されていることだ。農家の大きな手間となる選別作業を、ここでも地域で解決するべく最新の機械を導入し、農業の合理化を進めている。JA常陸笠間営農経済センター副センター長の福田健さんは「笠間でJAに出荷している栗農家は250軒ほどあり、9月以降は約10日毎に丹沢や岸根、利平、銀寄、筑波など様々な品種を収穫し、品種別に出荷していきます」と説明しながら、敷地内にある大きな栗専用冷蔵庫を見せてくれた。

茨城県は、栗の栽培面積・収穫量ともに全国一位を誇る。

栗は刈り取るのではなく、落ちたものを拾う「栗拾い」が基本。

拾う時はイガの両側を靴で踏んで押さえながら、火ばさみで取り出す。
「収穫したての新鮮な栗はそのまま出荷するほかにも、0℃の冷蔵庫で1カ月以上貯蔵して、通常の2~3倍の糖度に仕上げてから貯蔵栗『極み』というブランド名で出荷しています」
栗の産地ならではの貯蔵栗は人気が高く、11月頃から販売される予定だという。冷蔵庫の導入により、消費者はより長い期間、生栗を楽しめるようになった。

出荷直前の栗を前に、JA常陸笠間営農経済センター副センター長の福田健さん(中央)の説明を聞く。

大粒の栗を手にした「清澄白河フジマル醸造所」シェフの甲山雄也さんは「立派な栗と、同じ旬のサツマイモを使ってニョッキにしてみたらどうだろう」と、旬が盛り込まれた秋らしい料理をイメージする。
世界的なブランドを目指す、奥久慈しゃも。
奥久慈しゃもは野性味のある濃い味や独特の食感で人気も高く、国内ではすっかり定着している人気ブランド。昨年、地鶏としては全国初の地理的表示(GI)保護制度の対象に登録された。国内でのブランド確立はもちろん、海外での展開をも視野に入れてのことだという。

農業組合法人 奥久慈しゃも生産組合代表の高安正博さん。飼育から調理まで手掛ける高安さんのしゃもへのまなざしは、限りなく熱い。

奥久慈の杉の間伐材を利用した鶏舎で平飼いしている。
「肉質の優れたシャモ、名古屋コーチン、ロードアイランドレッドの交配によって生まれたのが、奥久慈しゃもです。通常のブロイラーの育成期間は50日ですが、しゃもの雄は125日、雌は155日かけてじっくりと成長させ、出荷体重は平均2kg~2.5kgまでになります。肉質は筋繊維が緻密で肉汁が豊富、野性味溢れる深いコクと歯応えも自慢です」

奥久慈しゃもはJA全農いばらきの「ポケットファームどきどき 茨城町店」でも販売。

この日、昼食をとった「ポケットファームどきどき 茨城町店」内「森の家庭料理レストラン」。地元の食材を使った日常に馴染む料理が種類多く並ぶ、ブッフェレストランだ。併設の直売所で食材の販売もしている。
奥久慈しゃもは長期間かけて育てるため、骨太なガラから取れる濃厚スープも人気。地元では、丸鳥をさばいて鍋にする奥久慈しゃも鍋をメニューに載せるところもあり、部位毎の肉の味わいを比較でき、人気だという。

「DEAN&DELUCA」F&B商品企画マネージャー境哲也さん。「DEAN&DELUCAでは地方食材のイベントをよく開くので、生産者やご当地ならではの食べ方や調味料の扱いも、料理と一緒に紹介できたら……」と構想が浮かんだ。

「Toro Gastro BarTokyo」エグゼクティブシェフの小河英雄さんは「焼鳥や鍋以外にも、たとえば唐辛子やフルーツでマリネした、南米風のシュラスコ風も面白いよね」と、しゃもを使った新たなメニューをイメージ。
山葡萄系日本ワインの新たな可能性
「つくばワイナリー」。
早朝からの茨城食材産地探訪も、いよいよ最後の1軒。一段と涼しい風が吹く日暮れ前に、筑波山の麓に広がるつくばワイナリーに到着した。
約1万本のブドウが植えられている畑を歩くと、葉の間のあちこちからたわわに実ったブドウが顔を出し、収穫されるのを待っている。口に含むと、甘さと香りがいっぱいに広がる。つくばワイナリーの代表である岡崎洋司さんは、2011年よりこの地でブドウ栽培をスタートさせ、委託醸造による初リリースは2014年から。故郷の茨城を、ワインを通じてもっと盛り上げていきたいという思いがある。

「つくばワイナリー」の責任者、岡崎洋司さん。今後はオーベルジュの建設も予定している。

筑波山を見下ろすブドウ畑には、太平洋から吹くミネラルを多く含んだ風が、山の麓にぶつかり、なだらかな丘を吹き抜けていく。
現在ブドウを育てワインを造っているのは、醸造家の北村工さん。栃木や宮城、ニュージーランドなどで醸造を学び、2017年につくばワイナリーに参加、今年からいよいよ自社ブドウで仕込みが始まる。
「つくばワイナリーのブドウ品種は、山葡萄とメルローの交配品種『富士の夢』が約5割、山葡萄とリースリングの交配品種『北天の雫』が3割、残りがメルロー、シャルドネ、マルスランの計5種で、山葡萄系の品種が主軸です。日本で生まれたブドウを使うことによって、日本ワインの面白さがより表現できると思います」

「日本ならではのワイン造りを突き詰めたい」と北村さん。

つくばワイナリーでは、5種類のブドウを栽培する。写真はメルロー。

全国の日本酒や日本ワインを扱う「LA MAISON DU 一升VIN」店主の岩倉久恵さんは「日本ワインの個性を感じるワインが生まれる、可能性に満ちたワイナリー。初リリースが楽しみです」。

「メゾン ジブレー」のオーナーパティシエ江森宏之さんは、ワインにする前の富士の夢の搾りたてブドウジュースを口にして「山葡萄らしい香りがいい。富士の夢の二番果で、ジェラートを作ってみたい。今年の収穫、手伝いに来ます!」と、新作ジェラートのアイデアを実行するべく、北村さん達と話が盛り上がっていた。

ふるまわれた搾りたてブドウジュースは、ワインにも負けない力強いブドウの味。
たくさんの生産者の想いを直に感じることができた、初秋の茨城ショートトリップ。「茨城県は農業を合理化する仕組みができつつあって、若い人も積極的に参加できる環境がある。おいしいものは当然で、その先にサステナブル、食べて体に良く動物にもストレスのないもの、無理にたくさん作るのではなく、できるものをできる範囲で作るような農業にしていくといいと思う」と藤丸さんは語る。
「東京から100キロ圏内にこんなに豊かな産地があるのは、東京で飲食店を営む者としてありがたい」「生産者のみなさんの苦労や思いを知り、実際にどんな環境で食材が育まれているのかを目にすることができて、料理の新たなイメージが湧きます」など、食のプロたちにとって刺激や発見の多い旅となった。

「茨城県は農業を合理化するシステムがある。品質よく、サステナブルな農業になればいいと思う」と「清澄白河フジマル醸造所」オーナーの藤丸智史さん。
DATA
▼ れんこん
◎ 稲敷農業協同組合 東部支店
☎ 0299-78-2141
▼ 有機野菜
◎ 仲居農園
☎ 0291-35-1300
▼ アールスメロン
◎ 茨城旭村農業協同組合 営農情報支援センター
☎ 0291-37-1661
▼ しゃも
◎ 奥久慈しゃも生産組合
☎ 0295-72-4250
▼ 栗
◎ 常陸農業協同組合 笠間営農経済センター
☎ 0296-74-4702
▼ ワイン
◎ つくばワイナリー
☎ 0299-46-7455
【問い合わせ先】
茨城県農産物販売促進東京本部
東京都大田区東海3-2-1大田市場事務棟4F
☎ 03‐5492-5411