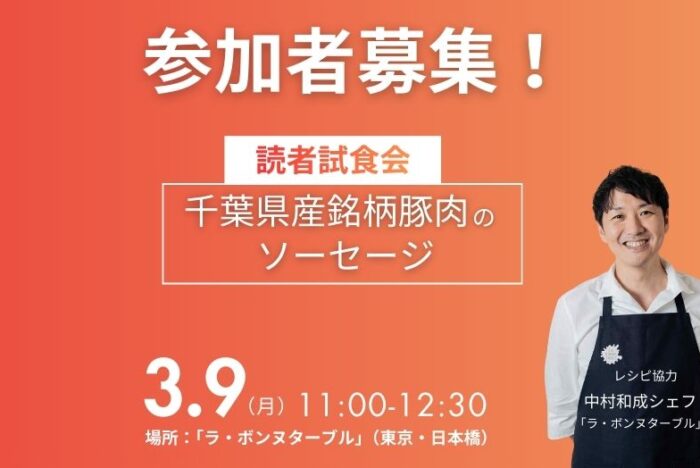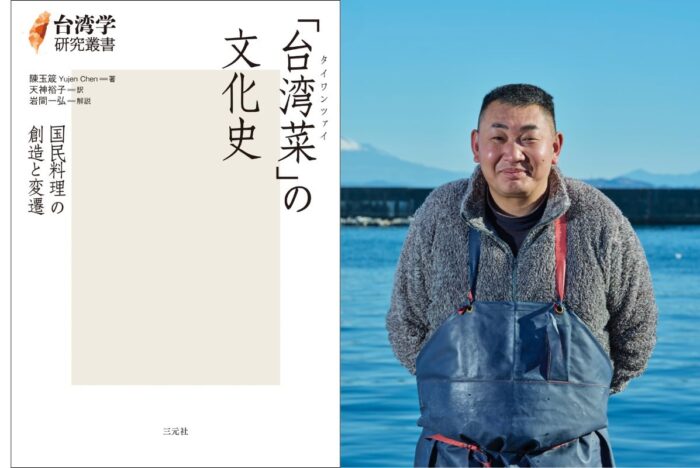都会と田舎をかき混ぜろ!シェ・イノ× 埼玉・ときがわ町「トカイナカハウス」晩餐会
【寄稿】ノンフィクション作家、トカイナカハウス主宰、神山典士
2025.03.03

photographs by Hikaru Ogawa
かたやフランス・ロアンヌの三ツ星「メゾン トロワグロ」と全盛時のパリの三ツ星「マキシム」。フランスの「都会と田舎」で学んだ故・井上旭シェフ(現代の名工)の本格フランス料理の伝統を今に伝える東京・京橋「シェ・イノ」。
こなた宮沢賢治が「注文の多い料理店」のモデルとした里山が広がる埼玉県ときがわ町。そこに2020年に誕生した「都会と田舎をかき混ぜる」をコンセプトとするコミュニティハウス「トカイナカハウス」。(トカイナカとは都心から1.5時間圏内を指す。地方分散型社会を目指すシンボルとなるエリア)
庭の梅も綻び始めた2月16日の一夜、両者が「ローカルガストロノミーの可能性」をテーマに「魅惑のアンサンブル」を奏でる晩餐会が開かれた。


極上の宴に参加できたのはわずかに8名。
比企郡エリアの野菜(多くは有機無農薬)や果物、黒毛和牛などをふんだんに使った世界に誇るシェ・イノのスペシャリテ!デザートはコンロを持ち込んで炎の饗宴・特製クレープ・シュゼット。ワインは小川町の完全自家栽培ビオ100%武蔵ワイナリーの「小川 小公子 2020 Extreme(エクストリーム)」。さらにグランヴァン「シャトー・ラフィット・ロートシルト2005」。バゲットもテーブルも椅子も和紙のテーブルクロスも全てときがわ町産の特注品。フルートのクラシック生演奏付き。シャンパンのマグナムボトルに始まりワインや日本酒(720ml)12本を開けて延々4時間。
ゲストが奏でる驚き笑い歌声歓声に包まれて、築50年の豪華7LDKの古民家は見事に共鳴していった—-。

最高峰の料理人が「田舎」を料理する
「この舌平目のソース、素晴らしい! 濃厚でキレがあって香り豊かでコクがある。シェ・イノのスペシャリテですか?」
4品目の「舌平目のブレゼ」が提供された時、一人の女性が驚きの声をあげた。
「はい、井上がパリのマキシムで学んできたアルベールソースです。さらにそれを日本で磨きをかけました」。シェフソムリエの伊東賢児が応える。
「アルベールさんはマキシムのシェフではなくてメートルドテル(支配人)ですよね?何故メートルがソースを?」隣に座る、俳優で「日本のワインを愛する会」の会長でもある辰巳琢郎が質問を重ねる。
「当時はメインダイニングでお客様の面前でソースを仕上げていたそうなんです。フュメ(魚のだし)にフォン(肉のだし)を混ぜています」
「だからか!今は白ワインを合わせてるけど、赤でもマリアージュすると思った」
「左様でございます。当店でもブルゴーニュのグランヴァンを合わせるお客様もいらっしゃいます。本日なら、『小川 小公子 2020 Extreme』に合わせても絶品かと」
「それだ!魚料理にあえて赤ワインを添える。そんなマリアージュ、カッコいいなあ!」
提供される料理に舌鼓を打ちながら、グルマン達の会話に花が咲く。

この日、晩餐会のテーブルに顔を揃えたのは、フードジャーナリスト、地元実業家、元バンカーの不動産コンサルタント、世田谷のご婦人、美術教師、地元古刹の住職、漫画家、そしてゲストの辰巳琢郎の8人だった。
料理するのはシェ・イノ総料理長、「現代の名工」古賀純二。ソムリエは同店社長でもあるシェフソムリエの伊東賢児。トカイナカハウスはゲストハウスでもあるが、厨房には家庭用の設備しかない。それでも二人はこの企画を相談された時、なんの躊躇いもなく「いいですよ、やりましょう」と即答している。

伊東は言う。「うちは井上シェフの時代から銀閣寺や薬師寺で50~60人の出前パーティーを経験しています。地方に出張するのはなんの抵抗もありません」
そう、改めてシェ・イノの創業者井上旭のフランス修業の足跡を振り返ると、半世紀の間三ツ星を維持している「メゾン トロワグロ」は田舎町ロアンヌ(ロワール県、人口3万5000人)にあり、7年間のフランス修業の最後に選んだ「マキシム」はパリにある。まさに「都会と田舎をかき混ぜる」というトカイナカハウスのコンセプトにぴったりだ。
というよりも、本来フランス料理の本質は地方にある。その地方独特の食材を使い、同じ土壌で育ったブドウからワインを作り、その土地の水で調理する。
だからリヨンから車で約2時間、サンボネ・ル・フロアにある三ツ星「レジス・マルコン」に行けば地元の山で採れたキノコ料理ばかりが20皿出てくる。ブルターニュ地方に行けば、オマール海老や牡蠣などの料理がメインになる。合わせるワインもいずれも地元産のものだ。特に頼まなければブルゴーニュやボルドーのグランヴァンは出されない。
そのことをフランス取材を通して体験した私は、トカイナカハウスを開設した当初から、「地元の食材を使って世界標準の料理を楽しむ=ローカルガストロノミー」の試みをトカイナカエリアでもやってみたかった。それは、日本の地方の食文化の現状を憂えればこその発想だった。
例えばトカイナカハウスのある埼玉県比企郡には、「すったて」という冷や汁料理がある。地元産の野菜と味噌の絡みがおいしい。あるいは武蔵野うどんという地元の太麺を、肉汁で食べるのも一般的だ。けれどそれらの料理が銀座のレストランで提供されるとは、地元の人間は思っていない。それは「田舎料理」だからだ。提供されたらむしろ「恥ずかしい」と感じるだろう。
あるいはときがわ町の有機野菜率は4.3%、小川町は19%(ともに耕地面積比率)という有機野菜王国だ。けれどそれらを一流レストランで使ってもらおうとはなかなか考えない。最近では「Farm to table(ファーム トゥ テーブル)」という動きもあるが、このエリアではまだその本格的な活動は始まっていない。
ならば余計に、名実共に日本の最高峰のレストランの料理人にこのエリアの生産物を使ってもらい、名うてのグルマンたちに喜んでもらおう。そうすれば地元の生産者の自信になる。エリア全体の農業や飲食関係者のモチベーションもアップする。私はそう考えた。
皿の上でのマリアージュ 根深ネギとオマール海老
事実、この日2皿目の「根深ネギとオマール海老のブレス仕立て」で、埼玉県鳩山町で生産する「根深ネギ(深谷ネギと同種)」を使ってもらった生産者、飯島紘一はこう語る。
「仕上がった料理を見て、うちの野菜をきれいに使ってもらって感動しました。高級食材のオマール海老とうちのネギが出会うなんて新鮮です。一般的にうちのネギは味噌汁の具材だったり煮物料理だったりが多い。キムチも漬けてます。飲食店で使ってくれているのはラーメン店や焼鳥店。洋食の文化は初めてだったので新鮮でした」


飯島夫妻は、約10年前にこの地にやってきた移住者だ。神奈川県に住んでいたが、「暖炉のある家に住みたい」という理由で埼玉県鳩山町に家を建てた。そこで家庭菜園から始め、妻の千春が農業大学校に通い、夫の紘一も2年後に会社を退職して農業に従事するようになった。
メインで生産するのは長ネギ。深谷ネギと同種の根深ネギをメインに数種類のネギとニンニク、ニンジン、ジャガイモ、ハーブ類など約30品目を約2.5ヘクタールの農地で栽培している。いまでは専業農家となり、JAには出荷せずに地元の直売所やレストラン、契約者などへの直接販売がメインだ。
実は今回、飯島夫妻にはもう一つの楽しみがあった。将来飲食関係に進みたいという希望を持つ次男が、ギャルソンとしてこの晩餐会を手伝うといいだした。父子は昨年末に京橋のシェ・イノでランチを取り、次男は緊張しながらも味わったことのないフランス料理(子羊のマリアカラスなど)の深みを経験し、当日を楽しみにしていた。
ところが次男は前夜の発熱で参加を断念。当日は晩餐会の途中に親子で挨拶に来ただけで、手伝いはできなかった。けれどこのことで、次男の気持ちはさらに前向きになったのではないかと飯島はいう。
「ご挨拶に行った時も古賀さんと伊東さんから学校の勉強も頑張れ! と声をかけていただきました。晩餐会の3日後から定期試験だったのですが、体調不良でも刺激になったようです。来年度から高校2年生になり栄養コースにいくようです。そこで勉強して飲食関係に進んで、将来はお父さんお母さんの野菜を使いたいと言ってくれています。今度の試験では学年で10番以内が目標とか。やはり一流の人の言動からは得られるものがあります。彼にとってこの出会いが人生のいいヒントになってくれたらと思います。」
一方、料理を担当する古賀はどんな感想をもったのだろうか。
晩餐会の約2カ月前。古賀と伊東はつれだってときがわ町を訪ねて、地元の料理研究家、白戸啓子の案内で地元生産者と会っている。その時の感想を古賀はこう語っていた。
「ときがわ町では素晴らしい生産者に出会いました。60歳になってから標高600メートルの土地を自分で耕して立派な農場『ファーム700』をつくったの岩瀬登志男さん。実山椒を地元の特産にしようと活動している『ときがわ山椒栽培協議会』山口富士生さん。そんな素晴らしい生産者の食材を料理するのが楽しみです」。この日の古賀の手元には、入間ケーブルテレビ内スマイル農場で生産しているイチゴやブロッコリーなども集まった。
メインディッシュの「ブッフ・ウェリントン(牛ヒレのパイ包み)」で使う黒毛和牛は、深谷で約3900頭を飼育する「尾熊牧場」のヒレ肉を使用した。

尾熊牧場の黒毛和牛を使ってみた感想を、古賀はこう語る。「尾熊牧場の黒毛和牛はブッフ・ウェリントンに最適な牛ヒレでした。しつこさの全くない程よいサシと繊維質です。丁寧な世話や厳選された飼料の賜物だと思います。なによりも肥育に使われるこの地の清らかな水もいい。自然の豊かさがなせる技です。またこのヒレ肉を使いたいと思いました」
ブッフ・ウェリントンは良質なヒレ肉にフォアグラ、トリュフ、シャンピニオンデュクセルを詰めパイで巻いて焼き上げる。ソースはペリグー。全てが渾然一体となり、素晴らしいハーモニーを奏でる。
良質な肉との出会いがあり、古賀にとっても料理人冥利につきる一皿になった。
埼玉・小川町生まれの芸術品、小公子ワイン
この日のもう一方の主役はワインだった。
オープニングはシャンパンのマグナムボトル。メインディッシュにはグランヴァン「シャトー・ラフィット・ロートシルト2005」。
そこまでの料理には、地元小川町武蔵ワイナリーの赤白を合わせる。オーナーの福島有造は前職の銀行員を辞めてブドウ栽培を始めて約14年。有機無農薬栽培という完璧主義のワイン造りを徹底してきた。

福島はこの会に3種類のワインを持ち込んだ。今回の取り組みにこんな期待を寄せていた。
「私のワイナリーではビオワインをつくっていますが、農薬や肥料を使わなければ不味くてもいいという考え方は毛頭ありません。農薬や肥料を使わないからこそ旨いブドウ、そしてワインができる。特にブドウが不味くなる成長ホルモン『ジベレリン』を極力分泌させないように栽培することに注力しています。今回のような機会で、シェ・イノの古賀シェフと伊東ソムリエ、その料理を味わうゲストのみなさまからご評価いただき、うちのワインを使ってもらえたら非常に励みになります」
世田谷から来たゲストのご婦人Eさんは、この日の午後早めに小川町にきて武蔵ワイナリーの畑を訪ね、福島のブリーフィングを受けた。
「うちではブドウの木は人間が管理しようとしていません。木本来の力を精一杯伸ばす栽培をしています。そうすると肥料も農薬もいらないんです」
福島は、ブドウ棚の上に雨よけのポリエチレンシートをはって雨が当たらないようにしている。こうすると病気にならない。メインで栽培する小公子は果皮が薄いから、収穫前に雨に当たると裂果してしまう。それも防ぐことができる。
婦人は自分の背丈よりも高く横に真っ直ぐに延びる太い枝を見て驚いていた。彼女の中では、ワイン用のブドウの畑では地面から真っ直ぐに背の低い木が延びているのが常識だと思っていたからだ。
その言葉を聞いて、『日本ワイン礼賛』(主婦と生活社)という著書を持ち日本産のワインの応援団を自認する辰巳琢郎はこう語った。「ワイン好きな人はフランスワインの味や生産様式に慣れているから、フランス式が手本になっています。ブドウの選び方もワインの味も、いかにフランス風になるかを競っている。でも日本は土壌も気候も違うんだから、日本にあった品種や生産方式、味を求めればいいと思います」
隣に座る漫画家で、パリ暮らしが長いさかもと未明も言う。「フランス人がもっとも嫌うのは自国の文化を大切にしないでフランス文化をマネする人。日本人なら日本の歴史伝統文化をしっかり語るほうか喜ばれます」

そんな会話が続く最中で、全員が「おっ!」と驚いた一本があった。福島がもちこんだ、「小川 小公子 2020 Extreme」。ブラックベリーを思わせる深く濃い色合いで、のど越しにも強烈なパンチ力がある。
ソムリエの伊東もテイスティングしながら、「このワインは凝縮された豊かな黒色果実、カシス、ブルーベリー、プラム、ブラックベリー等を彷彿させる風味が口中に満ちあふれますね。酸味、タンニン、アルコールのバランスもいい。若いですがとてもバランスのとれた秀逸なワインです。これぞ小公子ワインの最高峰、日本を代表するワインといっても過言ではないでしょう」と絶賛だ。


このワインのことを福島はこう解説した。「2020年はグランドビンテージで、8月2日に梅雨が明けたんですがそこからずーっと快晴だった。普通小公子は8月の後半に収穫をするのですが、エクストリーム用のブドウは通常収穫時にブドウを少量残し、そこからさらに2週間収穫を遅らせた。だから糖度が29度まであがったんです。そのブドウをアメリカオーク樽にいれて約2年間寝かせました。だから熟成も進んで、素晴らしい味わいになっています」
料理の皿を厨房に下げてきた時に、伊東は私に小声で言った。「このエクストリームだと、もしかするとシェトー・ラフィットよりもいいかもしれません。少なくともこの料理に合わせたら、エクストリームのほうが合うでしょう」
まさにジャイアントキリング!!
伊東の言葉を聞きながら、日本産のワインを奨励している辰巳も嬉しそうだ。
実際に古賀のスペシャリテである「ブッフ・ウェリントン」に舌鼓を打つゲストたちも、シャトー・ラフィットよりもエクストリームの方にマリアージュの軍配を上げていた。
その様子を見ながら、伊東は言った。「このワインならばシェ・イノでも使わせていただきたいと思います。肉料理に素晴らしく合う」。隣で福島は、思い描いていた言葉をもらえて照れ笑いを浮かべている。
問題は、エクストリームは年間800本程度しか生産できないことだ。
「他の木の生育状況を見ながら何割かのブドウをあえて摘み残すわけですから、最初から何リットル生産するという計算が立たないのです」。年間800本の、文字通りエクストリーム(最高峰)。
現在は直販で1万円の定価だが、シェ・イノでの登場や市場の評判次第では、価格は高騰するかもしれない。飲むなら今のうち!!そんな新しいヒーローの誕生の宴にもなった。

料理人と生産者がダイレクトに繋がる価値
一夜明けた月曜日。
出席したゲストのSNSやメールには料理やワインの感想、楽しかった宴の様子などがいくつもアップされていた。その中に、私には嬉しい投稿もあった。
「昨日は申し訳ありません。次男は今日は熱が下がって学校にいきました。昨日は古賀シェフと伊東さんにご挨拶だけさせていただきました」
根深ネギを提供した飯島紘一からだった。私はこう返した。
「ぼくらトカイナカハウスのスタッフはシェ・イノの晩餐会をやりきった。君は生産物を提供して古賀シェフに調理してもらった。武蔵ワイナリーはシェ・イノでワインを使ってもらえることになった。みんな自信を持ちましょう。君の生産物も定期的に使ってもらえるように、古賀さんにアピールしてみれば」
すると飯島はこう返してきた。「今度生産物をシェ・イノに送ってみます。地元の友人生産者のものも入れてみます。一度古賀さんに連絡いれますね。ありがとうございます」
飯島のリアクションこそ、私がこの企画に求めていたものだ。地域の生産者たちが一生懸命生産するレベルの高い食材を、国内外に雄飛させること。
生産者と料理人がダイレクトに繋がること。地域の食文化を世界レベルに引き上げること。そのための意識改革をすること。そして日頃の取り組みに自信を持つこと。
繰り返しその試みが行われれば、トカイナカエリアの食文化のレベルは間違いなく上がっていく。そうなれば、その食材と料理を食べたいと、国内外からグルメグルマンがトカイナカエリアにやってくる。地元の料理人たちも頑張る。
そうやって「都会と田舎をかきまぜれば」地域に賑わいが生まれ、経済も回りだす。
多くの地方にとって希望となる「ローカルガストロノミーの可能性」が、新たに芽吹いた一夜になった。
春炬燵前夜の余韻に北叟笑む 神山野良



◎「シェ・イノ × トカイナカハウス晩餐会」
企画:シェ・イノ(古賀純二、伊東賢児)、トカイナカハウス(神山典士)
協力:手漉き和紙工房谷野、ときがわ町木香館、たぬきのねどこatflowers浅沼靖江(嵐山町)
バゲット:ときがわ町森の家(窪田登)
黒毛和牛:尾熊牧場(深谷)
野菜果物:入間ケーブルテレビ、ちはるふぁーむ(飯島紘一、千春、千景)
スタッフ:小玉薫、村田陽子、荻原匡司(シェ・イノ1年生)
フルート演奏:永井あすか
照明:小川雅也
シェ・イノ公式サイト
(「料理通信」のNewsコーナーでは、食に関する新商品やサービス、イベント情報をお届けします)
関連リンク