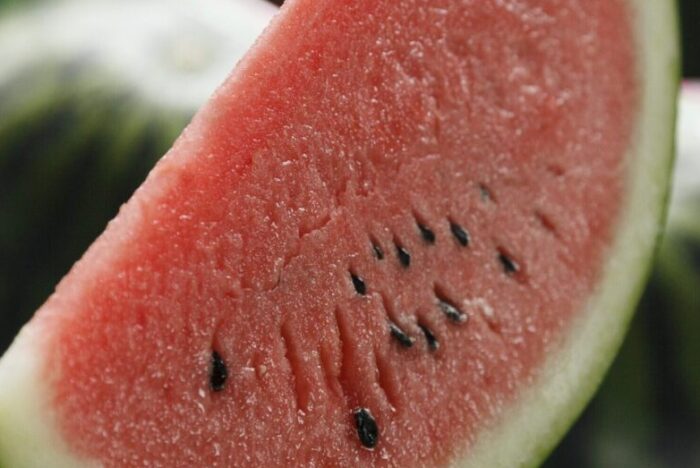その挑戦が、未来を変える。農業王国・茨城の継ぎ人たちの哲学
日本[茨城]
2022.09.08

【PROMOTION】
text by Saori Bada / photographs by Hiyori Ikai
東京からバスで北へおよそ1時間。車窓からの眺めは、ビルだらけの無機質な景色から、いつの間にか緑の濃淡で彩られる美しい田畑へと変わっていく。全国有数の農業県でもある茨城県には、独自の哲学を持って一次産業に取り組む生産者が多い。2022年7月初旬、鴨、ウイスキー、有機野菜、きのこ、4つの食材の生産者たちの現場を、食のプロ10人と訪ねた。
目次
- ■30年前からアニマルウェルフェアを実践/西崎ファーム
- ■販売までおこなう。だからゴールが見える。
- ■酒造りを起点に、県全体の農業を活性化させる/木内酒造
- ■糖度18度のトウモロコシは、手作業で虫から守る/レインボーフューチャー
- ■菌に合わせた寝床を作る。美しき “箱入り”きのこ/七会きのこセンター
30年前からアニマルウェルフェアを実践/西崎ファーム
早朝に訪ねた筑波山麓の養鴨場「西崎ファーム」には、ぴよぴよ、くわくわと鴨の元気な鳴き声が響く。ここでの鴨の暮らしは極めて自由だ。太陽の光を浴びながら広い敷地を気ままに散歩し、お腹が空いたら餌や農場の緑草や果樹を食べ、眠くなったら好きな場所で眠る。自然に近い環境の中で、24時間放し飼いなのだ。

1羽が動くと、追随して行動する習性を持つ鴨。敷地内にはブルーベリーやプラム、リンゴなどの木が植わり、自然落下した旬の果実をついばむ。

鴨の品種は肉質がやわらかでさっぱりした味のチェリバレー種が最も多く、鴨特有の強い香りと、濃い赤身の味が特長のクロワゼ種とチェリバレー種を掛け合わせた「志筑鴨(しづくがも)」も育成している。
「鳥は狭くてストレスの強い環境だと、忙しなくなり喧嘩が絶えず、病気にもなりやすい。逆に広くて自由な場ならリラックスでき、個々のペースで丈夫に成長します。自由があることで健康になるのは人と同じです」鴨たちの生態を教えてくれるのは、代表の清水司さん。
「一般的な養殖の鶏は生まれてから49日が出荷の目安ですが、ここでは85日間ゆっくり育てます。長く育てるので自然と運動量も増え、それは肉質にも大きく影響します。天気が良ければ散歩したり、木陰に座ってのんびりしたり、雨が降ったら泥遊びをしたり。こうして見学者が訪ねてくると、相手が餌をくれるのかどうか好奇心を持ってこちらを伺ったり。ほら、こっちを見てますよ」

代表の清水司さん。宮城県出身で、大学進学で茨城県へ。
清水さんは先代の西崎敏和さんから30年続く養鴨事業を2020年の5月に継ぎ、新たに歩み始めたばかりだ。二人を繋げたのは血縁でも地縁でもなく、仕事に対する哲学だった。
「ここを立ち上げた西崎さんは、30年前から動物の心身の健康を尊重し、飼育環境を重視するアニマルウェルフェアの考えを大切にされていて、私はそこに深く共鳴しました」
後継者問題で事業の存続に悩む一次産業従事者が多い中、 地縁も血縁もない若者が哲学に惹かれて事業を継いだというのは、間違いなく明るい事実だ。
「自分のような資金もノウハウもない若手でも、ここでなら自分の目指す仕事ができると思えた。養鴨を通じて、さらには農産物や畜産物の多くが輸入に頼らざるを得ない現状も変えていきたい。一次産業から、地域や国の経済を活性化したいという想いがあります」
食べさせる餌は素材単体で購入し、雛の時期から4つの成長段階に分けて全て独自に配合する。ワクチンや抗生物質などの薬剤は一切使わず、非遺伝子組み換え、酸化防止剤の入っていないものなど、人が食べても安全なものを選ぶ。乳酸菌を適宜配合することで鴨の腸内環境も整い、地面に落ちた糞も菌のおかげで自然と土に還る。だから、敷地内は特有の嫌な臭いも少ない。
動物の生育を、人の都合だけで合理化すべきではない。そう考える清水さんは、鴨の成長を“見守る”感覚で育てる。「人が鴨を育てるというよりも、環境を整えて健康に育ってくれるように見守る感覚です。ファームでは薬を一切使わないので、特に病気の発生には気を使います。毎日鴨たちを観察し、体調の変化はいち早く察知し、調子の悪そうな子がいたら隔離するなど常に先手を打ちます」

餌はトウモロコシやゴマ、魚粉、菜種油粕、脱脂大豆、牡蠣殻、玄米のほか、唐辛子やニンニク、ビール酵母などをブレンド。

ヒナは屋内で過ごす。人を怖がらず、清水さんが手を伸ばすと近寄ってくるほど人懐っこい。
販売までおこなう。だからゴールが見える。
西崎ファームが他の養鴨場と大きく違うのは、育てた後に肉を捌き、販売するところまでを一貫して行う点だ。現在スタッフは6人。餌作りから小屋や柵の増築など農場の環境づくり、さらに肉に加工すると畜や出荷までも全員で行う。
「育てて終わりではなく、最終的に肉を調理する料理人の感想や要望を直接受け、常に客観的に肉質を確かめることができる。それが環境づくりや餌の配合など、目指す味作りへのヒントになります。スタートからゴールまで市場をクリアに俯瞰して育てられるのが強みです」

2021年から卵の孵化にもトライしている。孵化させるための温度管理や環境づくりも、この1年の試行錯誤でかなり成功率が上がったという。
「とはいえ、やりたいことが多すぎて自分たちだけでは手が回らないところもあります。今後は、飼料用トウモロコシの栽培や、地元ワインの絞りかすを飼料に配合するなど、地元の農家や地域と連携して全体が活性化するような仕組みを考えていきたいと思っています」
ちょうど自分の料理に合う鴨を探していたという東京・神楽坂「膳楽房」の榛澤(はんざわ)知弥シェフは「どんな場所で何を食べてどう育ってきたかこの目で食材の背景を知ることはとても刺激になります」と鴨の味に期待を膨らませていた。

東京・神楽坂の中国料理「膳楽房」「智林」を営む榛澤知弥シェフ。
東京・白金のフランス料理店「アルゴリズム」深谷博輝シェフは「日本の家禽類はヨーロッパのものよりあっさりしているように思う。以前扱った鴨には、飼料の魚粉の味を強く感じたことがあって、フレンチの動物系のソースの味とバッティングするなと感じました」と最近気づいた家禽の味について話してくれた。

茨城県下妻出身の白金「アルゴリズム」深谷博輝シェフ。
東京・神谷町「空花」脇元かな子シェフは、「生産者も料理人も単なるおいしさの追求だけでは成り立たない時代。食材をどう育てるべきか、輸入に頼らず国産で経済を活性化したいという清水さんの考えには共感することが多い。何より、健康的な環境ですくすく育っている鴨を料理してみたいです」と嬉しそう。

東京・虎ノ門の日本料理「空花」の脇元かな子シェフ。
酒造りを起点に、県全体の農業を活性化させる/木内酒造
霞ヶ浦の豊かな水源を抱く茨城県は、もともと大麦や小麦の栽培が日本一だった土地。それがいつの間にか輸入小麦にとって変わられ、生産量は一時期大きく落ち込んだ。
2023年に創業200年を迎える茨城県の老舗酒蔵「木内酒造」は、こうした県内の一次産業の衰退に危機感を感じ、茨城県の麦作りの復興をかけて1996年よりビール造りを始めた。
誕生した「常陸野ネストビール」は僅か数年で世界的な賞を受賞し、今や世界規模でマーケットを広げている。さらに2016年からは茨城県産の大麦や小麦、米を使ったクラフトウイスキー造りを開始。2022年7月にいよいよ「日の丸ウイスキー The 1ST Edition」の初リリースとなった。

酒造り200年を迎える木内酒造の新しい試みが詰まったクラフトウイスキー。
ウイスキー造りに立ち上げから携わってきた洋酒製造部マネージャーの川崎裕一さんは、その特徴をこう話す。
「私たちが作るクラフトウイスキーは、茨城県産の大麦小麦はもちろん、日本酒造りで精米の際に出る米粉も原料にしています。これは日本酒の酒蔵からスタートしている私達ならではの試み。仕上がりの味わいにはオリエンタルな甘やかさ、ココナッツやミルクのようなまろみのある風味を引き出しています。そのままでも、炭酸で割って軽やかなハイボールとしてもおすすめです」

洋酒製造部マネージャーの川崎裕一さん。木内酒造のクラフトウイスキーは独自に培養する酵母で発酵させる。発酵にはステンレスタンクと木製タンクの2種類を使用し、複雑かつ華やかな香味を狙う。

蒸溜室。短めでストレート形状の単式蒸溜器でもろみなどの特徴のある香りを残す。2度の蒸溜を経てアルコール度数70%まで引き上げる。

最後はバーボン樽やシェリー樽など海外から集めた樽や、国産の桜樽などで熟成させる。
代表取締役社長の木内敏之さんは、自社の多岐にわたる酒造りを通じて、地域のみならず県全体、ひいては日本の農産物と加工品の在り方を考えている。
「私達のビールやウイスキー造りは、現在茨城県内の麦を年間およそ200トン規模で使っています。また、ウイスキーの廃液や麦のかすはこの八郷地域で育てられる豚の餌に活用し、その豚でソーセージや生ハムなど加工品を作り、それを提供できるレストランも建設中です。農業は加工品が伸びないと成長しません。つまり茨城県の農業をさらに活性化するためには、私たちのような地元のメーカーが自ら新しい商品を作り、原材料を地元から購入することで伸びていくのです。海外産に頼っている材料がどんどん国産に切り替わっていくように、私達はこれから茨城県産の材料に強くこだわっていきたい」

木内酒造代表取締役社長の木内敏之さん。
木内さんの話をひときわ興味深く聞いていたのは、東京・学芸大学「リ・カーリカ」堤亮輔シェフ。「周辺地域のさまざまな食材や人の持つ技術、才能を巻き込みながらアイデアを次々と商品化し、地域全体の価値を上げていく木内さんは、茨城県のフィクサーのような存在ですね。情熱に溢れていて素敵だし、商品の持つストーリーも魅力がある」

堤亮輔シェフ。東京・学芸大学のイタリア料理店「リ・カーリカ」、物販も併設する「リ・カーリカランド」ほか3店舗を展開する。
ウイスキー好きでもある東京・代々木上原の「クインディ」安藤曜磁(ようじ)シェフは、「木内さんのお酒に対する愛情が伝わる味です。甘やかで豊潤。調合のバランスの巧さも感じます。ああ、こういうお酒が好きな方なんだなぁと、人柄が見えるようなウイスキーです」

東京・代々木上原のイタリア料理「クインディ」安藤曜磁シェフ
また、東京・丸の内「パレスホテル東京」資材部部長の笹野洋介さんは、最近のローカルフードツーリズムを楽しむゲストに向けて、この地域が非常に魅力的だと感じたそう。「日本酒を起点に次々に新しいことに挑む木内さんの試みには、茨城県の食のストーリーが詰まっています。東京から僅か1時間という近さもあり、ローカルの美食を好む私達ホテルのお客さまに喜んでもらえる、魅力的なアドレスだと思います」

東京・丸の内「パレスホテル東京」資材部部長の笹野洋介さん
糖度18度のトウモロコシは、手作業で虫から守る/レインボーフューチャー
2000年に新規就農した茨城県筑西市「レインボーフューチャー」代表の大和田忠さんは、無農薬・無化学肥料で年間50品目以上の野菜を育てている。ベビーリーフやレタス、小松菜などの葉物からニンジン、タマネギ、ジャガイモと幅広いが、最近特に力を入れてきたのがトウモロコシの有機無農薬栽培だ。

レインボーフューチャー代表の大和田忠さん。2000年より脱サラして就農。
糖度が18度とフルーツ並みに甘くなるため、そのほとんどが虫と雑草との戦い。1000本から栽培をスタートし、最初の収穫はわずか200本。それが7年越しに7万本まで収量を増やし、ようやく採算が取れる筋道が見えてきたという。
「薬を一切使わずに虫の被害を最小限に食い止めるにはどうしたらいいか。これが大きな課題でした。育てながら調べていくと、鍵はトウモロコシの髭にありました。虫がまず髭に卵を産みつけ、それが成長して中の実を食べてしまうからです。普通なら農薬で処理しますが、私達は薬は使いませんから1本ずつ髭を切るしかない。地味で大変な作業ですが、実らせるためには欠かせません。ちょうど7月初旬の今が最盛期ですが、無農薬だからこそ、生で食べて欲しい。このホワイトコーンは、ものすごくジューシーで甘いんです」

虫を寄せ付けるトウモロコシの花もすべて手で落とす。手塩にかけても3割は不良となる。

トウモロコシは白色と黄色の品種を半々で育てる。黄色の品種の花粉が白色の品種につかないように、植える場所は300m以上離す。

甘くて水分量が多いプラチナコーン。皮が口の中で残ることもない。
肝心の土作りは、地元の学校給食やスーパー、関東一円で出る野菜の残渣を集め、2年間完熟させて堆肥化して土にすき込む。余計な肥料も加えず土と微生物だけで育てられた野菜は、再び地元のスーパーやレストランなどで使われる。結果として循環型農業が叶っている。
畑の脇では、採れたてのホワイトコーンを試食。茨城・水戸「レストランOhtsu」大津高彬さんは、「地元でこんなに味わいのある野菜を作っていることを知って嬉しい。採れたての新鮮な野菜を料理でお出しできるのは、地元のレストランの特権ですから」と顔をほころばせた。

茨城・水戸のフランス料理店「レストラン オオツ」大津高彬さん。
菌に合わせた寝床を作る。美しき “箱入り”きのこ/七会きのこセンター
味わい、見た目、風味や食感。どれもが満足のいくレベルに育てるにはどうしたらいいか。 舞茸やたもぎ茸、あわび茸や花びら茸、木耳など、さまざまなきのこの菌床栽培を長年手がける「七会(ななかい)きのこセンター」代表理事の中川幸雄さんは、繊細なきのこ栽培の難しさを語る。

「七会きのこセンター」代表理事の中川幸雄さん。
「天然の環境に限りなく近い状況を作るために、欠かせないのは温度と湿度の管理です。さらに、標高の高い山と同じように空気内の酸素濃度の調整も必要になります。きのこは菌が成長するのをゆっくりと待つ栽培方法なので、人は生育の様子を観察しながら、環境を整えることしかできません。じっくりと時間をかけて育てたきのこは、食感や旨味も強く、収穫後の長期保存も可能になります」
きのこの培養は、おがくずとふすまなどをあわせた土台、培地(ばいち)に種菌を植え付け、成長を見守る。培地は舞茸ならクヌギやナラ、花びら茸ならカラマツ、などと種菌によって栄養帯が分けられる。

培地はビンや袋に詰められる。温度20~23℃、湿度80%前後に保たれた培養室で3週間から3カ月かけてきのこ菌を培地に蔓延させる。全体が白くなってきたら菌が回った証拠。

菌が回ったら、培地は培養室へ。菌の種類に応じて温度と湿度、CO2濃度が菌の成長に適した数値で厳密に管理される。30℃を超えると死滅する菌が多いので、夏は電気エネルギーが生命線。

ヒラタケは強めに光をあてて育てると、濃い茶色になる。

花びら茸は比較的低い20~25℃の環境で成長。培地の袋を突き破って多方向へ成長する。旨味の濃い茎を好んでまとめ買いするシェフもいるそう。

シイタケは菌床玉を櫛状に刺して吊るす「つり棒栽培」を採用。温度帯はやや高めの22~27℃。シイタケの菌は水をかけるなど、刺激して成長を促す。同じハウスで、野生では日本最大級の大きさまで育つニオウシメジの育成にも挑戦中。
きのこを収穫して残ったおがくずは葉物の栄養に最適なので、近隣の農家で活用してもらい資源を循環させている。結果、きのこの育成に関する廃棄物はほぼセロだという。
東京・代々木上原「竹韻飄香(ジュユィンピャオシャン)」廣瀬文彦シェフは、珍しい花びら茸や白木耳なども栽培されていることに興味津々。「中国料理ではきのこは人気の高い高級食材。味はもちろん、色や形など見た目の美しさも大切ですが、こちらではその点も非常に気を配っている。自分の料理にどう使おうかと刺激されます」と、新たなメニューのアイデアを話してくれた。

東京・代々木上原の中国料理「竹韻飄香」廣瀬文彦シェフ(左)
一日駆け足で回った今回の茨城食材ツアー、日本各地の生産者を訪ねている人にはどう映ったのだろう。産地と消費者を繋ぐ場を作る「良品工房」代表でバイヤーの白田典子さんは、「良いものを作っている人は、人そのものも魅力的。今回巡った方々も、新しいことを恐れずに、絶えず挑戦を繰り返している。作りながら考え、実践と改良を重ねている姿勢が印象的で、自分もそうありたいと思いました」と話す。
普段から地元の生産者を訪ね歩き、地産地消を実践している地元茨城県水戸市の「COLK(コルク)」加藤大恭シェフは、「茨城の生産者の方々が、料理人と同じように試行錯誤して生産物を作っていることを改めて実感しました。シェフとして3年目ですが、僕の店の使命は地元の素材で地元ならではの魅力を伝えること。今回巡った生産者の方々の想いも、料理を通じてお客さまにしっかり伝えていきたいです」と、茨城食材への想いを新たにした様子だった。

東京駅で地域産品を販売する「ニッコリーナ」を展開する「良品工房」代表でバイヤーの白田典子さん(中央左)。地元茨城県水戸市のイノベーティブレストラン「COLK」加藤大恭シェフ(中央右)
▼ 鴨
◎ 西崎ファーム
☎ 0280-87-0462
▼ クラフトウイスキー
◎ 木内酒造
☎ 029-212-5111
▼有機野菜
◎レインボーフューチャー
☎0296-20-3339
▼ きのこ
◎ 七会きのこセンター
☎ 0296-70-7088
【問い合わせ先】
茨城県営業戦略部東京渉外局県産品販売促進チーム
東京都千代田区平河町2-6-3 都道府県会館9F
☎ 03-5212-9093
この旅の経験をもとに、10軒の店舗で茨城の魅力を届けるメニューを展開中です。
関連リンク