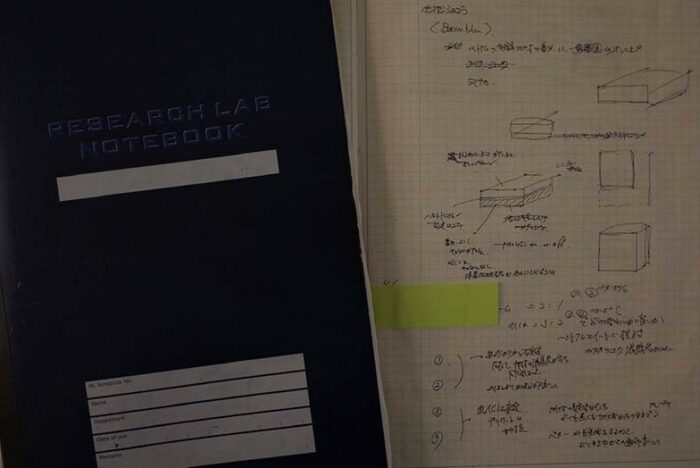香港
関根拓さん連載 「食を旅する」第9回
2017.11.21

連載:関根拓さん連載
「食べること」の意味と楽しさを教えてくれた。
高校生の頃、沢木耕太郎さんの『深夜特急』は僕らのバイブルだった。
トルコの受刑者たちの間で、脱獄することを「ミッドナイトエキスプレスに乗る」と言ったそうだ。
僕らは決して日本から脱出することを望んでいたわけではない。
ただ、非日常である外国の景色を夢見ていた。
日本を後にした沢木さんが最初に訪れるのが香港だった。
彼の描くこの街は一言一句エキゾチックな魅力に溢れていた。
「いつか香港に行ってみたい」
この作品を読んだことがある人なら誰もがそう思っていたに違いない。
2003年、僕は初めて香港を訪れた。
香港島に降り立つと、想像していたよりもさらにけたたましい騒音と芳醇な食べ物の香りが五感を刺激する。
慌ただしい日常の中に溶け込んだカオスは、潮の香りのする湿気と相まって、喧騒の隅々にまで漂っていた。
まさにウォン・カーワイの映画の世界だ。
この溢れ出るエネルギーは一体どこから来るのだろうか。
都市が放つオーラをこれだけ凝縮して感じられることも珍しい。
汗のにじむ亜熱帯気候、世界最高の人口密度、エネルギッシュな気質、押し寄せる外国人。
この街と人を描写するどんな言葉にも「過多」な形容がよく似合う。
トルコの受刑者たちの間で、脱獄することを「ミッドナイトエキスプレスに乗る」と言ったそうだ。
僕らは決して日本から脱出することを望んでいたわけではない。
ただ、非日常である外国の景色を夢見ていた。
日本を後にした沢木さんが最初に訪れるのが香港だった。
彼の描くこの街は一言一句エキゾチックな魅力に溢れていた。
「いつか香港に行ってみたい」
この作品を読んだことがある人なら誰もがそう思っていたに違いない。
2003年、僕は初めて香港を訪れた。
香港島に降り立つと、想像していたよりもさらにけたたましい騒音と芳醇な食べ物の香りが五感を刺激する。
慌ただしい日常の中に溶け込んだカオスは、潮の香りのする湿気と相まって、喧騒の隅々にまで漂っていた。
まさにウォン・カーワイの映画の世界だ。
この溢れ出るエネルギーは一体どこから来るのだろうか。
都市が放つオーラをこれだけ凝縮して感じられることも珍しい。
汗のにじむ亜熱帯気候、世界最高の人口密度、エネルギッシュな気質、押し寄せる外国人。
この街と人を描写するどんな言葉にも「過多」な形容がよく似合う。


「食」は何と言ってもこの街のハイライトだろう。
エネルギーに満ちた街の食文化はいつも生命力に溢れている。
文字通り、人間のエネルギーは食べることによってもたらされるのだから、当然と言えば当然かもしれない。
しかし、この得体の知れない高揚感は、香港の食が生命活動以上に文化として成熟している何よりの証拠だ。
人で溢れかえる飲茶も、行列の絶えないワンタン屋台も、深夜の海鮮レストランも、その全てが街の一部として輝きを放っている。
香港は僕にとって早い段階で「食べること」の意味と楽しさを教えてくれた場所であった。
以来、幾度となく、世界中の人を惹きつけて止まないこの土地を訪れた。
エネルギーに満ちた街の食文化はいつも生命力に溢れている。
文字通り、人間のエネルギーは食べることによってもたらされるのだから、当然と言えば当然かもしれない。
しかし、この得体の知れない高揚感は、香港の食が生命活動以上に文化として成熟している何よりの証拠だ。
人で溢れかえる飲茶も、行列の絶えないワンタン屋台も、深夜の海鮮レストランも、その全てが街の一部として輝きを放っている。
香港は僕にとって早い段階で「食べること」の意味と楽しさを教えてくれた場所であった。
以来、幾度となく、世界中の人を惹きつけて止まないこの土地を訪れた。
どうしたら、昔ながらの仕事をこの目で見られるだろう。
ここ数年、僕のこの街への片思いは少しずつ成就され始めていた。
香港の同世代のシェフたちとパリで仕事を通じて知り合うことが増えていったのだ。
「Ho Lee Fook」のJowette Yu、「Little Bao」のMay Chow、「Le Garçon Saigon」のBao La。
今の香港を語る上で欠かすことのできないトップランナーたち。
僕らは毎晩ワインバーに繰り出しては、これからの料理の話をした。
皆それぞれ状況は違えど、想いは一つ。
「ソウルフルなアジアのフレーバーをもっとたくさんの人に楽しんでほしい」
好きな料理の話をしていると、時間はいつもあっという間に過ぎてしまうのであった。
香港の同世代のシェフたちとパリで仕事を通じて知り合うことが増えていったのだ。
「Ho Lee Fook」のJowette Yu、「Little Bao」のMay Chow、「Le Garçon Saigon」のBao La。
今の香港を語る上で欠かすことのできないトップランナーたち。
僕らは毎晩ワインバーに繰り出しては、これからの料理の話をした。
皆それぞれ状況は違えど、想いは一つ。
「ソウルフルなアジアのフレーバーをもっとたくさんの人に楽しんでほしい」
好きな料理の話をしていると、時間はいつもあっという間に過ぎてしまうのであった。

仲間の香港のトップシェフ達とともに。向かって左に「Le Garçon Saigon」のBao La、右に「Ho Lee Fook」のJowette Yu、「Little Bao」のMay Chow。
気が付けば、最後に香港に行ってから早くも3年が経とうとしていた。
店のオープン前に新古品の中華食器や蒸篭を買いに行ったきりだ。
「そうだ、今年の夏は飲茶の店でスタージュをしよう」
僕はそう春先に思い立つと、夏を迎えるのが楽しみで仕方がなかった。
しかし、中国の伝統的なキッチンでは研修をするのが非常に難しいと聞いていた。
というのも、中国では未だに技は身につけたら、自分の地位を守るために、もっぱら隠すものなのだそうだ。
点心の具材の配合も店のブレインのみが知り、定年退職するシェフですら自分の秘蔵のレシピと共に店を去るという。
どうしたら、昔ながらの仕事をこの目で見ることができるのだろうか。
僕はこの計画を友人たちに相談することにした。
すると拍子抜けするほどの速さでMayが点心と広東料理の老舗「MOTT32」でのスタージュをオーガナイズしてくれた。
8月初頭の香港はとにかく暑かった。
80%を超える湿度と30℃を超える気温、立っているだけで汗が溢れ出してくる。
「この気候と坂道のおかげで、香港の人はどんなに食べても太らないのだ」と、Mayが以前言っていたのを思い出した。
僕は久しぶりの香港で、過呼吸気味の気分を抑えるために、大きく深呼吸をした。
明日から待ちに待った研修の日々だ。

「MOTT32」にて。
スタージュの初日はいつも朝早く目が覚める。
少しの不安と大きな期待を持って新しい調理場に入るのが、今でも僕は大好きだ。
セントラル地区にある「MOTT32」にたどり着くと、Leeシェフが自ら出迎えてくれた。
店のコックコートに袖を通すと、僕は恐る恐る香港随一の調理場へと足を踏み入れた。
大英帝国風のシックな客席から正面にガラスを挟んで見える調理場には4台のウォックが並ぶ。
炎を点火すると、グォーという凄まじい騒音とともに熱気が一気に立ちこもる。
この図太い熱源に負けじとシェフたちは力強く鍋を振る。
油通しされた緑の野菜たちが白湯と乳化して、いかにもおいしそうだ。
時折見せる繊細な味付けの所作も、たっぷりと自信にあふれていて美しい。
隣の部屋に移ると、今度は全くの別世界だった。
10名ほどのシェフが黙々と手先に注意を集中させている。
蝦餃、小籠包、焼売、包、エッグタルトが次々と眼の前で仕上げられていく。
点心専門のこの室内は、早朝の豆腐屋を思わせる湯気で溢れていた。
僕はシェフたちに混じって様々な成形の作業を体験させてもらった。
中国語が全くわからない僕に、彼らは一生懸命身振り手振り教えてくれた。
もちろん、多少の研修で難しい技術が身につくほど甘いものではないと充分に承知している。
それでも料理に対して改めて真摯で謙虚な気持ちになれるこの時間こそがスタージュの醍醐味なのかもしれない。
少しの不安と大きな期待を持って新しい調理場に入るのが、今でも僕は大好きだ。
セントラル地区にある「MOTT32」にたどり着くと、Leeシェフが自ら出迎えてくれた。
店のコックコートに袖を通すと、僕は恐る恐る香港随一の調理場へと足を踏み入れた。
大英帝国風のシックな客席から正面にガラスを挟んで見える調理場には4台のウォックが並ぶ。
炎を点火すると、グォーという凄まじい騒音とともに熱気が一気に立ちこもる。
この図太い熱源に負けじとシェフたちは力強く鍋を振る。
油通しされた緑の野菜たちが白湯と乳化して、いかにもおいしそうだ。
時折見せる繊細な味付けの所作も、たっぷりと自信にあふれていて美しい。
隣の部屋に移ると、今度は全くの別世界だった。
10名ほどのシェフが黙々と手先に注意を集中させている。
蝦餃、小籠包、焼売、包、エッグタルトが次々と眼の前で仕上げられていく。
点心専門のこの室内は、早朝の豆腐屋を思わせる湯気で溢れていた。
僕はシェフたちに混じって様々な成形の作業を体験させてもらった。
中国語が全くわからない僕に、彼らは一生懸命身振り手振り教えてくれた。
もちろん、多少の研修で難しい技術が身につくほど甘いものではないと充分に承知している。
それでも料理に対して改めて真摯で謙虚な気持ちになれるこの時間こそがスタージュの醍醐味なのかもしれない。
友人は最高の先生でもある。

香港を去る前にどうしても「チャイニーズ・ロースト」の技術を見て帰りたいと思っていた。
「チャイニーズ・ロースト」は、マリネした肉の内側と外側の水分をほどよく飛ばすために吊るして乾燥させ、タンドリーに似た炭火オーブンで皮はパリッと身はジューシーに焼き上げる。香港を代表する料理の一つだ。
JowetteとBaoが快く「いつでも自分の店に見に来たらいい」と言ってくれた。
僕は、「Ho Lee Fook」で鴨と焼豚を、「Le Garçon Saigon」では仔豚のローストを学ばせてもらった。
彼らにとってはごく当たり前の仕事でも、僕にとっては喉から手が出るほど尊い技術。
師事するシェフのいない僕らにとって、友人たちは最高の先生でもあるのだ。

Jowetteの店「Ho Lee Fook」にて。

Baoの店「Le Garçon Saigon」にて。
JowetteとBaoとはキッチンの外でもいつも一緒だった。
早朝は香港最大のアバディーン市場に魚の買い出しに行った。
Baoが市場に向かうタクシーの中で言う。
「香港は海産物がとにかくいい。それはもともと漁師の島だったからで、香港は香港である前に魚の街だったんだ」
車はちょうど市場からほど遠くない漁師の集落を通り過ぎる。
僕はこんな何気ない時間がいつまでも続けばと切に願う。
最終日の朝、僕らは「陸羽茶室」にいた。
昔ながらの雰囲気を残す老舗の飲茶だ。
新聞を片手にジャスミンティーを嗜む老紳士。
白色の制服に身を包む給仕。
アーモンドのスープをすする老父婦。
Jowetteは言う。
「古くからリビングもない狭い住居に住む香港の人間にとって、飲茶は大切なサロンなんだ」
僕はまた少しだけ香港のことが理解できたような気がした。
早朝は香港最大のアバディーン市場に魚の買い出しに行った。
Baoが市場に向かうタクシーの中で言う。
「香港は海産物がとにかくいい。それはもともと漁師の島だったからで、香港は香港である前に魚の街だったんだ」
車はちょうど市場からほど遠くない漁師の集落を通り過ぎる。
僕はこんな何気ない時間がいつまでも続けばと切に願う。
最終日の朝、僕らは「陸羽茶室」にいた。
昔ながらの雰囲気を残す老舗の飲茶だ。
新聞を片手にジャスミンティーを嗜む老紳士。
白色の制服に身を包む給仕。
アーモンドのスープをすする老父婦。
Jowetteは言う。
「古くからリビングもない狭い住居に住む香港の人間にとって、飲茶は大切なサロンなんだ」
僕はまた少しだけ香港のことが理解できたような気がした。
関根 拓(せきね・たく)
1980年神奈川県生まれ。大学在学中、イタリア短期留学をきっかけとして料理に目覚め、料理人を志す。大学卒業後、仏語と英語習得のためカナダに留学。帰国後、「プティバトー」を経て、「ベージュ アラン・デュカス 東京」に立ち上げから3年半勤務。渡仏後はパリ「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」で腕を磨き、二ツ星「エレーヌ・ダローズ」ではスーシェフを務める。その後、パリのビストロ、アメリカをはじめとする各国での経験の後、2014年パリ12区に「デルス」をオープン。世界的料理イベント「Omnivore 2015」で最優秀賞、また、グルメガイド『Fooding』では2016年のベストレストランに選ばれた。2019年春、パリ19区にアジア食堂「Cheval d’Or」をオープン。
https://www.dersouparis.com/
https://chevaldorparis.com/