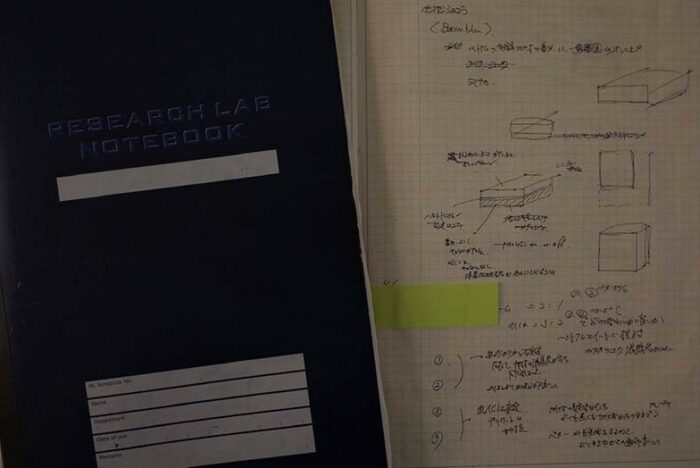カレー、水野仁輔さん。
関根拓さん連載 「食を旅する」第8回
2017.09.07

連載:関根拓さん連載
東京の街とカレー。
高校生の頃、下北沢のタイ料理店で食べた「ココナッツカレー」は未だ訪れたことのないバンコクの街を思い描かせた。
コリアンダー、レモングラス、コブミカン、ココナッツ、赤唐辛子。
汗が溢れ出るほどに騒々しい辛さの中にもエキゾチックな甘さや爽やかなフレーバーが漂っている。
一般的なカレーライスの経験しかない僕にとって、それはとても衝撃的な出来事だった。
大学生の時分、裏原宿で食べた「カフェのカレー」は少し澄ました東京そのものだった。
丁寧に作られたそのカレーは、見え隠れするホールスパイスのせいか、香りがとても洒落ている。
ライスとカレーの境界線上には色とりどりの揚げ野菜とフレッシュハーブがトッピングされている。
小さい鍋で温めながら水分が飛んで縁が焦げ始めたような香りも新鮮だ。
こんなにきれいでおいしそうなカレーライスはそれまで見たことがなかった。
社会人になってからしばらくの間、僕は西葛西に住んでいた。
西葛西には日本最大のインド人コミュニティーがある。
だから「インド人の作るカレー」に出会うのにもそう時間はかからなかった。
休日の昼間、散歩をしていると、インド人が仕込んだカレーを銀のポットに入れて自転車でどこかへ運んでいる。
僕は、街に漂うこのカレーの香りこそが遠いインドという国の香りなのだと信じていた。
この街では無数にある店選びも、まずはインドの北か南を選ぶところから始まる。
自分は、ナンを食べたい時は北を、ライスかドーサが食べたい時は南を選んでいた。
店に入ると、上級者はインド人に混じって、カレーを優雅に手で口へと運んでいる。
素材に応じて使い分けられるスパイスによって、カレーの色は赤にも黄にも緑にも変化した。
僕はこの街で、まだ見ぬインドという国の膨大なカレーの情報量に途方にくれた。
コリアンダー、レモングラス、コブミカン、ココナッツ、赤唐辛子。
汗が溢れ出るほどに騒々しい辛さの中にもエキゾチックな甘さや爽やかなフレーバーが漂っている。
一般的なカレーライスの経験しかない僕にとって、それはとても衝撃的な出来事だった。
大学生の時分、裏原宿で食べた「カフェのカレー」は少し澄ました東京そのものだった。
丁寧に作られたそのカレーは、見え隠れするホールスパイスのせいか、香りがとても洒落ている。
ライスとカレーの境界線上には色とりどりの揚げ野菜とフレッシュハーブがトッピングされている。
小さい鍋で温めながら水分が飛んで縁が焦げ始めたような香りも新鮮だ。
こんなにきれいでおいしそうなカレーライスはそれまで見たことがなかった。
社会人になってからしばらくの間、僕は西葛西に住んでいた。
西葛西には日本最大のインド人コミュニティーがある。
だから「インド人の作るカレー」に出会うのにもそう時間はかからなかった。
休日の昼間、散歩をしていると、インド人が仕込んだカレーを銀のポットに入れて自転車でどこかへ運んでいる。
僕は、街に漂うこのカレーの香りこそが遠いインドという国の香りなのだと信じていた。
この街では無数にある店選びも、まずはインドの北か南を選ぶところから始まる。
自分は、ナンを食べたい時は北を、ライスかドーサが食べたい時は南を選んでいた。
店に入ると、上級者はインド人に混じって、カレーを優雅に手で口へと運んでいる。
素材に応じて使い分けられるスパイスによって、カレーの色は赤にも黄にも緑にも変化した。
僕はこの街で、まだ見ぬインドという国の膨大なカレーの情報量に途方にくれた。
カレーを理解するためにインドへ。
振り返れば、カレーはいつも生活のどこかにいた。
母親のカレー、キャンプで作るカレー、食堂のカレー、賄いで食べるカレー、蕎麦屋のカレー。
インドから英国を経由して日本に伝わったカレーはすっかり日本の食文化の一部となっていた。
カレーに欠かせないターメッリクの消費量がインドに次いで世界第2位なのも頷ける。
日本に育った僕らは子供の頃からカレーの英才教育を受けてきたと言えるのかもしれない。
「カレーを1から自由に作れるようになりたい。」
僕は自然にそんなことを考えるようになっていた。
ルーに頼らない、カレー粉ミックスにも依存しない、カレーの世界を見てみたかった。
それでもどこから手をつけていいのかさっぱりわからない。
インドにも行った。
僕は、カレーを理解するにあたって、実際にインドでインドのカレーを味わう必要があると思っていた。
そして、インドにこそ本物のカレーがあると信じて疑わなかった。
しかし、食べ進めるうちに、彼の地のカレーは日本のカレーと全く別のベクトルを向いていることに気が付いた。
旨味を重視して味わいを重ねて行く日本のカレーと対照的に、インドのカレーは素材を引き立てるスパイスの香りに重点が置かれていた。
「面白い。カレーに正解などないのかもしれない」
近しい親戚ながらも、長い時間をかけて別々の運命を歩んできたどちらの家系にも共感が持てた。
母親のカレー、キャンプで作るカレー、食堂のカレー、賄いで食べるカレー、蕎麦屋のカレー。
インドから英国を経由して日本に伝わったカレーはすっかり日本の食文化の一部となっていた。
カレーに欠かせないターメッリクの消費量がインドに次いで世界第2位なのも頷ける。
日本に育った僕らは子供の頃からカレーの英才教育を受けてきたと言えるのかもしれない。
「カレーを1から自由に作れるようになりたい。」
僕は自然にそんなことを考えるようになっていた。
ルーに頼らない、カレー粉ミックスにも依存しない、カレーの世界を見てみたかった。
それでもどこから手をつけていいのかさっぱりわからない。
インドにも行った。
僕は、カレーを理解するにあたって、実際にインドでインドのカレーを味わう必要があると思っていた。
そして、インドにこそ本物のカレーがあると信じて疑わなかった。
しかし、食べ進めるうちに、彼の地のカレーは日本のカレーと全く別のベクトルを向いていることに気が付いた。
旨味を重視して味わいを重ねて行く日本のカレーと対照的に、インドのカレーは素材を引き立てるスパイスの香りに重点が置かれていた。
「面白い。カレーに正解などないのかもしれない」
近しい親戚ながらも、長い時間をかけて別々の運命を歩んできたどちらの家系にも共感が持てた。
カレーという言語を話し始めるようになっていた。

2010年、『かんたん、本格! スパイスカレー』(MARBLE BOOKS)という本が発売される。
スパイスから作るカレーの工程が「ゴールデンルール」という法則によって説明されていた。
僕はこの本に出会った時の衝撃を今でもよく覚えている。
レシピを羅列した文献こそあれど、カレー作りを体系立てて教えてくれる本はそれまで存在しなかった。
インド人でも意識しているか疑わしいカレーのルールが、この本の中では明文化されていた。
僕はこのゴールデンルールのおかげで、やっと向き合っていくべきカレー作りの指標ができた。
言い換えれば、カレーを自由にデザインしていくための教科書を手にしたのだった。
著者は「東京カリ~番長」の水野仁輔さんだった。
カレーファンの間では言わずと知れた有名人だ。
彼は広告代理店に勤めながら、趣味としてカレーと付き合っていた。
45冊を数えるカレー本の出版は趣味という領域をはるかに超えてはいるものの、会社員という立場をとることによって、自由にカレーにアプローチしていた。
水野さんの初期の代表的な活動が「東京カリ~番長」だ。
様々な分野のスペシャリストから構成されるこのカレー集団は常にユーモアに溢れる活動を行っていた。
「出張カリ~」に始まり、「公園カリ~」、「カリ~フェス」、「ブログカレー」、「カレー展」、「聴くカレー」と多岐に渡る。
カレーを目的ではなく飽くまでコミュニケーションの手段としているところも新しかった。
僕はそんな微笑ましいカレー好きの大人たちをいつも外側から眺めていた。
僕はパリでカレーを作り続けた。
一度カラクリを理解すると、面白いようにカレーはできた。
レシピを闇雲に習得するだけでなく、そのルールを意識することで、自分のカレーをコントロールできるようになっていた。
ルールを知ることで、あえてルールから外れることも可能になった。
僕はよく、料理をマスターすることは外国語を習得するのに似ていると思っている。
文法をマスターした上で単語を紡ぐと一皿になる。
僕は、水野さんの著書のおかげで、カレーという言語を話し始めるようになっていた。
スパイスから作るカレーの工程が「ゴールデンルール」という法則によって説明されていた。
僕はこの本に出会った時の衝撃を今でもよく覚えている。
レシピを羅列した文献こそあれど、カレー作りを体系立てて教えてくれる本はそれまで存在しなかった。
インド人でも意識しているか疑わしいカレーのルールが、この本の中では明文化されていた。
僕はこのゴールデンルールのおかげで、やっと向き合っていくべきカレー作りの指標ができた。
言い換えれば、カレーを自由にデザインしていくための教科書を手にしたのだった。
著者は「東京カリ~番長」の水野仁輔さんだった。
カレーファンの間では言わずと知れた有名人だ。
彼は広告代理店に勤めながら、趣味としてカレーと付き合っていた。
45冊を数えるカレー本の出版は趣味という領域をはるかに超えてはいるものの、会社員という立場をとることによって、自由にカレーにアプローチしていた。
水野さんの初期の代表的な活動が「東京カリ~番長」だ。
様々な分野のスペシャリストから構成されるこのカレー集団は常にユーモアに溢れる活動を行っていた。
「出張カリ~」に始まり、「公園カリ~」、「カリ~フェス」、「ブログカレー」、「カレー展」、「聴くカレー」と多岐に渡る。
カレーを目的ではなく飽くまでコミュニケーションの手段としているところも新しかった。
僕はそんな微笑ましいカレー好きの大人たちをいつも外側から眺めていた。
僕はパリでカレーを作り続けた。
一度カラクリを理解すると、面白いようにカレーはできた。
レシピを闇雲に習得するだけでなく、そのルールを意識することで、自分のカレーをコントロールできるようになっていた。
ルールを知ることで、あえてルールから外れることも可能になった。
僕はよく、料理をマスターすることは外国語を習得するのに似ていると思っている。
文法をマスターした上で単語を紡ぐと一皿になる。
僕は、水野さんの著書のおかげで、カレーという言語を話し始めるようになっていた。

友人から、ある日、水野さんがパリにしばらく滞在するという噂を聞きつけた。
僕はどうしてもこの機会に彼に会ってみたかった。
カレーを作れば作るほど、疑問は湧くばかりで、彼に直接聞いてみたいことが山ほどあった。
7区のクラシックなビストロで僕らは待ち合わせをした。
僕は、テーブルを挟んで向かいに座るカレー界のスターに緊張した。
「ヨーロッパには御旅行で、それともカレーの研究で?」
もちろん答えは後者だった。
「日本のカレーの飴色タマネギのルーツを探しに、イギリスに3カ月と今はパリに1週間来てるんだ」
すぐには意味のわからない期待通りのカレーっぷりに僕は興奮した。
「インドカレーを長年研究してきたけど、やっぱり日本人だから日本のカレーが一番だなって気になってね」
「だから、インドから日本にカレーの伝わる中継地点であったイギリスに目をつけたわけですね」
と僕は不意に飛び出た自分の優等生的な切り返しに感心した。
「そうなんだ」
と彼が満足そうな表情を浮かべると、僕の緊張は一気に和らいだ。
タイミングよく運ばれてきたオニオングラタンスープで話はさらに盛り上がり、ワインを飲みながらのカレー談義は夜更けまで続いた。
僕は「欧風カレー番長」になった。

2014年、「東京カリ~番長」は新規メンバーを募集していた。
今なら自分でも何かできることがあるかもしれない。
憧れのカレー集団の一員として活動することを考えると、カレー作りにも今まで以上に力が入った。
海外からでも参加できるものかは疑問だったが、僕はこのチャンスを逃すわけにはいかなかった。
就職活動さながら、応募用紙にモチベーションレターを添えて、日本へと送った。
1カ月後、「東京カリ~番長」からメールが届く。
残念ながら結果は落選だった。
しかし、水野さんからの文面が続いた。
それは「欧風カレー番長」という新しいグループを作るからメンバーにならないかというものだった。
欧風カレーとは、インドからイギリスを経由して日本に伝わった、いわゆる日本のカレーである。
彼は長年のカレー研究の集大成として、カレー界のみのコンテクストに収まることなく、あらゆる分野の知恵を取り入れながら、日本人の誰もが旨いと思う新しい日本のカレーを開発しようとしていた。
僕は、カレーがもたらしてくれたカレーのためのこの大役を二つ返事で引き受けた。
僕は100年前のカレーと100年後のカレーを思う。
100年前からのたゆみない先人たちの努力のおかげで、今日の日本のカレーがあるのなら、僕は100年後のカレーのために、ファンとして少しでもその進化に貢献できればと思っている。
関根 拓(せきね・たく)
1980年神奈川県生まれ。大学在学中、イタリア短期留学をきっかけとして料理に目覚め、料理人を志す。大学卒業後、仏語と英語習得のためカナダに留学。帰国後、「プティバトー」を経て、「ベージュ アラン・デュカス 東京」に立ち上げから3年半勤務。渡仏後はパリ「アラン・デュカス・オ・プラザ・アテネ」で腕を磨き、二ツ星「エレーヌ・ダローズ」ではスーシェフを務める。その後、パリのビストロ、アメリカをはじめとする各国での経験の後、2014年パリ12区に「デルス」をオープン。世界的料理イベント「Omnivore 2015」で最優秀賞、また、グルメガイド『Fooding』では2016年のベストレストランに選ばれた。2019年春、パリ19区にアジア食堂「Cheval d’Or」をオープン。
https://www.dersouparis.com/
https://chevaldorparis.com/