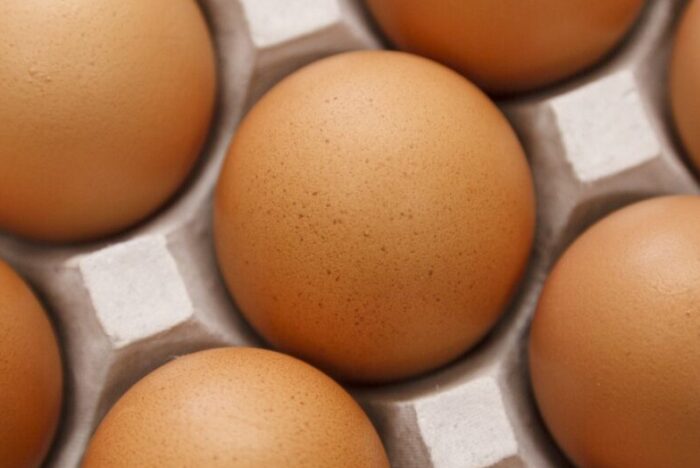こうして料理人は自然の代弁者になる。5人のシェフが茨城の産地に教わること。
日本[茨城]
2025.10.06

【PROMOTION】
text by Miko Fujita / photographs by Atsushi Kondo
全国有数の農業県・茨城。2025年8月、県内各地では史上最高気温を記録するなど、例年を大きく上回る厳しい猛暑に見舞われましたが、豊かな自然環境と積み重ねられた生産者たちの工夫によって、この土地ならではの力強い食材が生み出されています。
イタリアン、フレンチ、モダンアジア、東京で活躍する5人の実力派シェフとともに、茨城の「おいしい」食材の背景にある土地の記憶や作り手の営みに出会う、日帰り旅をリポートします。
目次
- ■「海」「土」「山」の恵み、オリジナルブレンドの追肥/多品種米
- ■金砂郷の山間地域で育ててこそ実力を発揮する/常陸秋そば
- ■子どもの頃は、“腹(はら)作り”。丈夫な腹ができても“ドカ食い”NG/常陸牛煌
- ■肥料も農薬も水もなし、スパルタ環境で「生きる力」を見守る/小松菜、ルーコラ
「海」「土」「山」の恵み、オリジナルブレンドの追肥/多品種米
最初に向かったのは茨城県西部・筑波山の裾野に広がる田園地帯、筑西市桑山。江戸時代から代々300年以上稲作を続けている大嶋農場だ。「おいしいお米を作って、消費者に届けること」をモットーに、「百笑米」という独自のブランドを立ち上げ、米の生産だけでなく、精米、販売まで一貫体制で運営している。



広大な敷地内には母屋を中心に、オフィスや資材倉庫、育苗用ハウスなどが並ぶ。ここ大嶋農場の特徴は、健康でしっかりとした苗作り、その苗床の土作りから手掛けていること、そして「海」「土」「山」の恵みをバランスよく組み合わせた独特の肥料にある。
小貝川や五行川などの河川も流れ、古くから米の栽培に適した土壌として知られているが、代表の大嶋康司さんは、「米づくりに適している土地とはいえ、平野なので夏はこの通り暑いです。気候に頼ることはできない。その分、肥料など栄養や工夫、生産努力をしなくてはなりません」と話し始めた。
「田植えが終わればすぐ翌年の苗床作りが始まり、夏の太陽熱を利用した土の消毒、堆肥作りまで、全てを自家で行なうのは健康な稲に育て、おいしい米を収穫するためには独自の工夫が必要不可欠だから」と大嶋さん。
苗床の土は7、8月の日差しの強い時期にハウスの中で太陽熱消毒をし、有機肥料も屋敷森の落ち葉やコウモリの糞など、研究を重ねて成果を感じたものを混ぜ込み発酵させる。
圃場に撒くのは、「海からの恵み」では牡蠣殻とにがり、「土からの恵み」は稲以外の草の成長を抑えることに役立つ米の籾殻や米糠、そして、サトウキビやテンサイから砂糖を作った後に残る液体、糖蜜。「山からの恵み」はこの地域の土着菌が付いている笹だ。
「こうして米作りの可能性を追求していくうちに、ミネラル豊かな天然塩や光合成の促進が期待できるハチミツなども、米の旨みに繋がることを実感でできるようになりました。今では、沖縄産『雪塩』や国産ハチミツ、鰹節エキスも散布しています」という話に、「なんと贅沢」とシェフたちは驚きを隠せない表情で顔を見合わせた。



続けて、屋敷森の周辺に広がる田んぼへ。強い日差しを受けた緑鮮やかな田んぼが見渡す限りに広がっている。「うちの田んぼは緑が綺麗でしょう? 夏の間中水を枯らさないよう川から引いてきた水を流しているんです。猛暑の今年は毎朝の作業。田んぼの土がひび割れてしまってはせっかくの稲が台無しになってしまうからね」
大嶋農場の驚くべき特徴はこれだけではない。主力品種の「コシヒカリ」「ミルキークイーン」のほかに、暑さに強い品種として近年注目される「にこまる」「にじのきらめき」のほか、パラパラとした食感の「華麗舞」、粒がしっかりとして味がよく染み込む「和みリゾット」、酢のなじみが良いすし用の米「笑みの絆」、パン用の米「ミズホチカラ」「笑みたわわ」など、なんと38品種を育て、販売している。

「米は嗜好品です。人それぞれに好みがありますし、料理によって種類を選べた方がいい」と大嶋さんの米を愛するが故の熱弁は止まらない。
収穫した米は低温倉庫で保管され、注文が入ってから精米して出荷する。「おいしい」「楽しい」を実直に追い求める大嶋農場の取り組みは、常に食べる人のことを思って料理を考えるシェフたちも共感するものが多く、料理人として、そしてビジネスを考える上でも学ぶことの多い経験となった。



◎大嶋農場
茨城県筑西市桑山3327
☎0296-57-3774
https://www.hyakusyoumai.co.jp/
金砂郷の山間地域で育ててこそ実力を発揮する/常陸秋そば
次の訪問地は、茨城県北部、玄そばの名産地として名高い常陸太田市金砂郷赤土地区。そば職人、そば通からも高い評価を受ける極上品種、「常陸秋そば」の発祥の地だ。
久慈川の中〜下流域の東側に位置し、清らかな川の流れと山の緑に囲まれたのどかな農村の眺めに心癒される。山間のカーブをくねくねと上がっていく道すがら、山あいの傾斜地の小さな区画にそばの畑が点在する。水捌けがよく昼夜の気温差が大きいということが見るだけで感じられる地形だ。


案内してくれたのは、「いばらき蕎麦の会」の幹事長兼事務局長・野上公雄さん。そばの歴史、そして茨城県のそばに詳しいのはもちろん、心から地元の誇るべき「常陸秋そば」を愛し、情報を発信している人物だ。
「そばは茨城よりも信州が有名ですが、それは生産量の問題なんです。茨城のそばは香りと風味は優れていますが、収量が少なく地元消費が中心でした」とそばの魅力を話し始めた。
「茨城県は江戸時代からそばの産地として知られていました。かの水戸黄門様は、水戸藩で活用できそうな特産品として全国から作物や家畜を導入してその活用を奨励していたのですが、そばも黄門様が金砂郷赤土に導入され、それが土地の気候風土の影響を受けて「金砂郷在来」になっていったものと推定されています。これが『常陸秋そば』の先祖となったわけです」
茨城県にはこの「金砂郷在来」のほかに「那珂在来」「大子在来」「猿島在来」などいくつかの在来種がそれぞれに適した環境で栽培し続けられ、各地に中小の産地があったが、形状や粒、品質にばらつきがあったという。


江戸時代からの歴史あるそばどころに相応しいそばを作り振興を図ろうという機運が高まり、1978年から県をあげてそばの新品種育成に取り組んだ結果、選ばれたのが、香りがよく、外皮が黒いなど最もおいしいと評判の「金砂郷在来」の中でも赤土地区の畑で栽培されていたものだった。
以降選抜を繰り返し、1985年、ついに「常陸秋そば」が茨城県の奨励品種として採用。実が大きく粒の揃いもよく、安定して高い品質を保っていることから国内産のそばの中でも最高峰と評され、高値で取引きされている。また、種も流通し、茨城県のみならず日本各地で栽培されるようになった。しかしながら「この金砂郷の山間地域のような環境で育ててこそ最良の実力を発揮するので、やはりこの地で育てられたものを食べていただくのが一番ですよ」と野上さん。
畑見学の後は「いばらき蕎麦の会」の工房でそばの会の名人による打ち立て、茹でたてのそばをいただく。「常陸秋そばの真骨頂は、そばを口に含んだ時の甘味と鼻腔に広がる芳醇な香りです。ただ、そばの香りは繊細ですから、まずはつゆをつけずそばだけ食べてみてください」と野上さんが説明する前から、「プリモパッソ」の藤岡シェフは、そばだけを口に含み風味を堪能。「そばだけで十分においしい」と結局何もつけずに平らげていた。







金砂郷の山間のそば畑が可憐なそばの花で真っ白になるのは9月中旬から下旬。
10月半ばから収穫され、新そばが提供される11月には日本各地からそばファンが訪れるという。まさにこれからが「常陸秋そば」の季節。「新そばの時期にぜひいらしてくださいね」という野上さんの言葉に一同大きく頷いてバスに乗り込んだ。
◎JA常陸
☎0294-72-9111
子どもの頃は、“腹(はら)作り”。丈夫な腹ができても“ドカ食い”NG/常陸牛煌
世界的に高いブランド力を誇る和牛。だが、肥育技術の向上が進み、単に霜降り肉、ブランド牛、黒毛和牛というだけは差別化が難しい時代になってきている。
そんな中、茨城県は県内の銘柄牛、常陸牛の生産、流通、販売、研究など様々な立場の有識者で構成する検討委員会を立ち上げ、常陸牛の中からさらに厳選し、常陸牛の“トップ・オブ・トップ”を目指し、新ブランド「常陸牛 煌(きらめき)」を立ち上げた。
風味や口溶けの良さに関わる「オレイン酸」や口当たりの良さに関わるきめ細やかな霜降り「小ザシ」など、おいしさの理由に着目した全国初の基準である。
今回訪ねたのは、検討委員会の中心的存在であり、肥育から食肉加工まで行う牛肉のスペシャリスト・橋本畜産の橋本武二さん。ブランドに甘んじることなく、飼料や肥育環境の改善、疾病対策などいかに安全で品質高く、おいしい肉を提供できるかを業界内でも先駆けて取り組み、県内トップの実績を誇る。
基準を新たにした煌に関しても、2024年に最も多く認定されたのが橋本さんの牛だ。



その秘訣をシェフたちが尋ねると「愛情だよ」と答えは意外にシンプル。
「人間の赤ちゃんを育てるのと同じ。言葉は話せないけれど、目を見たり、体を触ったり、動きを見ていれば何を求めているのかちゃんと伝わってくる。快適な環境づくりとおいしい食事を心がけて、ストレスを溜めたり病気で辛い思いしないように目をかけ手をかけて育てることが大切なんです」と橋本さん。
大きく健康に育てる秘訣は「子どもの頃は栄養よりも“腹(はら)作り”。胃を丈夫にするようオリジナルの配合で飼料を作っているが、その内容は企業秘密。牛の体質に合わせて量を決めて与えているそうだ。丈夫な“腹作り”ができたら、食べ放題にするそうだが、30カ月以上かけてゆっくり肥育するため、乳酸発酵させた稲藁や麦、トウモロコシなどを細かくして、やや食べにくい形状にしてドカ食いできないような工夫をしているという。



西洋料理「ベッラ・ヴィスタ」の齋藤慎太郎シェフが「サシが少なめが好まれる傾向なのですが、煌はどうなのでしょう?」と尋ねると「黒毛和牛も霜降り信仰が薄れてきましたよね。サシが多いと脂っこい、胃もたれすると言われますが、脂の成分がオリーブオイルの主成分であるオレイン酸を多く含むように育てています。オレイン酸の融点は約13℃と低いのが特徴で、煌はオレイン酸比率が55%以上。ですから、風味や口溶けがよく、やわらかさと旨みを感じながらもあっさり。それでいて食べた後に“おいしかった!”という印象が残るんです」
従来の常陸牛の飼育機関は28カ月程度だが、「煌」は月齢30カ月以上と定義。「さらに60日ほど長く飼育することで、赤身の旨みやオレイン酸が増すだけでなく、より細やかなサシになりやすく、おいしさに差が出るのです」と橋本さん。
より厳しい基準を設けることで常陸牛のみならず、日本の和牛の質を底上げしていきたいという思いがあってのチャレンジだ。


「ロッツォ シチリア」の中村シェフは、「ブランド牛は日本中に多数あり、おいしさの基準もさまざま。その中からどう選んでいくか悩ましいところだが、こうやって産地を訪ね、それを食べ手につなげる役割が料理人にはあることを改めて感じた。縁あって知り合うことができた橋本さんの常陸牛。ぜひ料理してみたいですね」と話してくれた。
◎橋本畜産
茨城県東茨城郡茨城町宮ケ崎1874-1
☎029-293-7796
https://www.hashimoto-beef.co.jp/
肥料も農薬も水もなし、スパルタ環境で「生きる力」を見守る/小松菜、ルーコラ
最後に訪れたのは、笠間市の郊外に3箇所の圃場を持ち、76棟のビニールハウスで小松菜、ホウレン草、ルーコラを有機栽培している「ヴァレンチア」。茨城県は、有機栽培に挑戦する農家が盛り上がりを見せているが、ここは有機で独立したい若者が知識と経験を求めて働きにくる、そんなモデルケース的存在でもある。
社長の池之上透さんは実は鹿児島出身。しかも農業で起業したのは15年前の2010年、それまではITで起業し、25年以上世界中を飛び回り活躍していたという。
「IT業界でお金が貯まったら農業で起業したいという思いはずっと持っていました。実家は畜産業を営んでいるのですが、私は有機で野菜を育ててみたくて土地を探し、出合ったのがこの場所です」



数ある候補地の中で決め手になったのは「水です」と池之上さん。
「この地は江戸時代から水が枯れたことがないそうです。水質検査も完璧な数値でした。農家にとって水ほど大切なものはありませんからここしかない、と決めました」。池之上さんは、さらに100メートル掘ったところから「油田のように湧き出る」良質な水を使っているという。
ヴァレンチアの有機農法は、野菜自身が持つ「生きる力」を最大限に引き出すというもの。ハウス内に種を蒔き、最初に水を与えてからは収穫時期まで余程のことがない限りハウスはクローズしてできるだけ虫をシャットアウト。肥料も農薬も水も与えないスパルタ環境の中、しっかり根を張り、自力で土から水分と養分を吸収する「生きる力」を頼りに成長させるやり方だ。収穫時まではハウスのビニール越しに見守るだけという。


だが、ハウスの扉を閉めていても葉っぱを食べる虫や雑草をゼロにすることはできない。そのため「夏の間はハウスの地面に透明のビニールを張って太陽熱消毒をしています。13年ほど前、空気を与えないことで草が生えず、防虫効果もあると本で知りました。敷地の広範囲にビニールを貼る作業は骨が折れますし、コストもかかりますが」と苦笑い。
雑草対策は、数えきれないほど試行錯誤した。「黒ビニールを張ったその周囲6〜7mを深さ1メートルほど掘り下げて端材のチップを積み上げてみたこともあります。効果はあったのですが、カブトムシが幼虫を産みに来て、大量発生・・・。近隣の農家さんから苦情があって、諦めました」。独自の工夫でトライ&エラーを繰り返して、現在は黒ビニールのみに落ち着いている。
また、このエリアは竜巻が発生しやすく、ハウスのビニールが飛ばされる被害も何度か受けている。とはいえ、「農業というのは自然相手ですからトラブルも苦情も当たり前のこと。それでも、好きなことをやっているのでトラブルを克服する工夫が楽しいというか、面白いというか」と終始笑顔の池之上さん。

それにしても気になるのはこの猛暑でもビニールハウスの中の野菜たちはほんとうに生き延びるのか?ということ。ルーコラをはじめ野生味のある葉物野菜をたくさん使う「アンディ」の鈴木康哉シェフが尋ねたところ「夏は50℃くらいまで上がります。気温が33℃を超えたらミストを出していますが、この暑さに対応できるのが小松菜とルーコラだったというわけです。夏は1カ月で収穫できますが、ホウレン草はちょっと痩せてしまいますね。今年は夏のホウレン草は諦めました。冬は3カ月くらいかけて育ちますから味も濃くなりおいしさが増しますよ。早く夏が終わってほしいですね」
野菜の味については、「自分の力で生き抜いた野菜なので味わいは濃厚。歯応えもしっかりとしています。私たちの野菜は安心安全が誇り。食は命の源ですから野菜のパワーで笑顔になっていただけたらという願いを込めて作っています」と池之上さん。
小松菜とルーコラのビニールハウスを特別に開けてもらい、味見。「私は甘い野菜より、ちょっと辛みがある野菜が好みなので、そういう味に育っています。いかがですか?」と心配そうな池之上さんに、「おいしい!」「驚くほどやわらかい!」と口々に答えるシェフたち。「ルーコラは密に種を蒔くとやわらかく育つんですよ」とホッとして池之上さんの表情が笑顔に戻った。



「びっしりと育っている野菜の収穫も大変そう。手仕事ですか?」という質問には、「その点では茨城県は恵まれています。ゴルフ場がたくさんあり、そこで働く調理師の方々がアルバイトに来てくれるんです。ナイフ使いがプロで、手早く美しい切り口。料理人さんの技術って素晴らしいですね」と褒められ、シェフたちも「収穫を手伝いに来てみたい」と嬉しそうだった。

◎ヴァレンチア
茨城県笠間市泉2519
☎0299-37-6533
https://www.valentia.jp/
◎茨城県営業戦略部県産品販売課
☎ 03-5212-9093
関連リンク